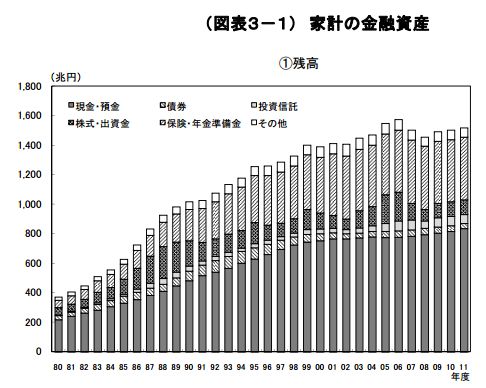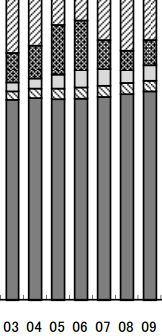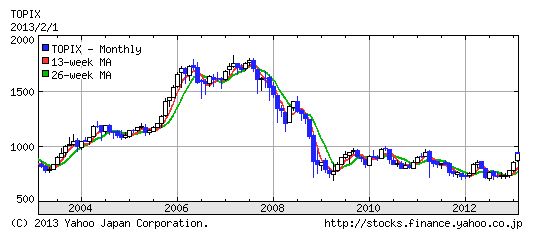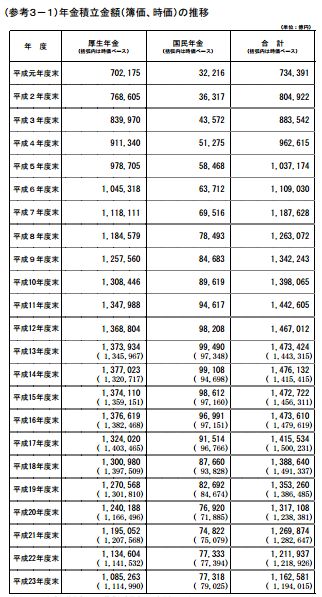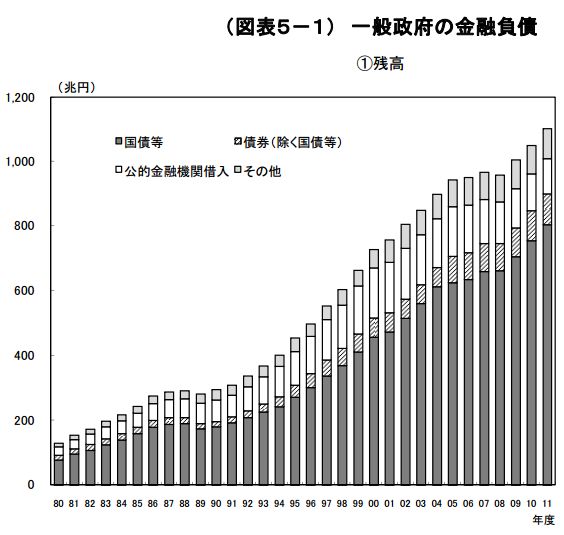過去に支払をおこなったものの現在価値を知りたく、物価上昇率やリスクフリーレートとしての日本国債の推移を知りたかったのだが、データが公開はされているがすぐに使えるような状態になっていないのでそれなりの加工を要した。ついでなので公開しておく。
物価参考データ消費者物価指数と、日銀の過去の金利情報を元に1970年~2013年までの表をつくった。データが無い部分については0%としている。ダウンロードしたエクセルの青字の部分を書き換えれば、累計の現在価格をしることができる。遺産相続などで遡ってごにゃごにゃしそうなときに使って下さい。
物価指数も国債の金利も毎月の前年比を平均して年度の平均値になおしている。エクセルのマクロで計算しているのでマクロを含んだまま公開しておくが、メインのシートを触るだけであれば動かす必要はない。採用したい金利の年数などを変更したいときなどは自分で変更してください。
↓ダウンロードはこちらから
長期金利表(オフィス2007以降をつかってね。)
| 年度 | 実質物価上昇率 | 日本国債金利 |
| 1970 | 0.00% | 0.00% |
| 1971 | 6.30% | 0.00% |
| 1972 | 4.91% | 0.00% |
| 1973 | 11.57% | 0.00% |
| 1974 | 23.18% | 8.23% |
| 1975 | 11.91% | 8.31% |
| 1976 | 9.37% | 8.49% |
| 1977 | 8.18% | 7.56% |
| 1978 | 4.21% | 6.49% |
| 1979 | 3.70% | 7.83% |
| 1980 | 7.76% | 8.75% |
| 1981 | 4.94% | 8.33% |
| 1982 | 2.75% | 8.05% |
| 1983 | 1.90% | 7.77% |
| 1984 | 2.27% | 7.27% |
| 1985 | 2.08% | 6.61% |
| 1986 | 0.62% | 5.35% |
| 1987 | 0.11% | 4.85% |
| 1988 | 0.68% | 4.87% |
| 1989 | 2.29% | 5.08% |
| 1990 | 3.10% | 6.88% |
| 1991 | 3.28% | 6.38% |
| 1992 | 1.74% | 5.35% |
| 1993 | 1.26% | 4.35% |
| 1994 | 0.68% | 4.36% |
| 1995 | -0.08% | 3.46% |
| 1996 | 0.13% | 3.12% |
| 1997 | 1.71% | 2.37% |
| 1998 | 0.66% | 1.53% |
| 1999 | -0.34% | 1.74% |
| 2000 | -0.66% | 1.78% |
| 2001 | -0.73% | 1.33% |
| 2002 | -0.91% | 1.27% |
| 2003 | -0.25% | 0.99% |
| 2004 | -0.01% | 1.50% |
| 2005 | -0.28% | 1.38% |
| 2006 | 0.24% | 1.74% |
| 2007 | 0.06% | 1.68% |
| 2008 | 1.38% | 1.49% |
| 2009 | -1.34% | 1.35% |
| 2010 | -0.70% | 1.22% |
| 2011 | -0.28% | 1.12% |
| 2012 | -0.04% | 0.86% |
| 2013 | 0.00% | 0.78% |
肝心のところはWebでもみれるように表にしておく。
物価参考データ消費者物価指数 中分類 前年同月比(昭和46年1月~最新月)
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001033702&cycode=0
各年の総合物価上昇(各月前年度比)の年度平均を採用
過去の金利情報
http://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/kako.htm
※74~89 は国債9年ものの金利を採用 、90年~ 新発10年ものの金利 金利がないものについては0%とした