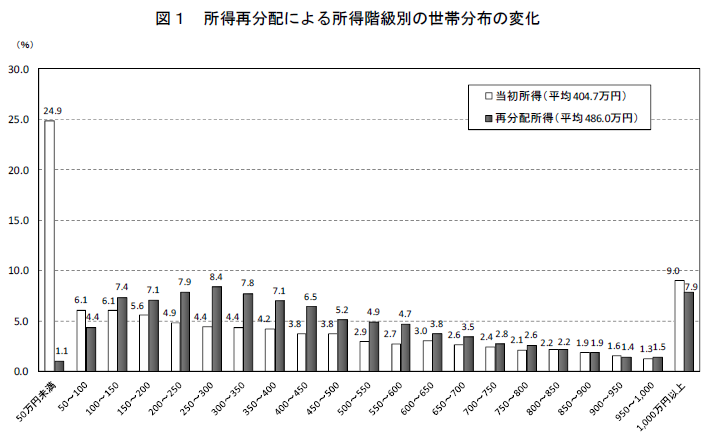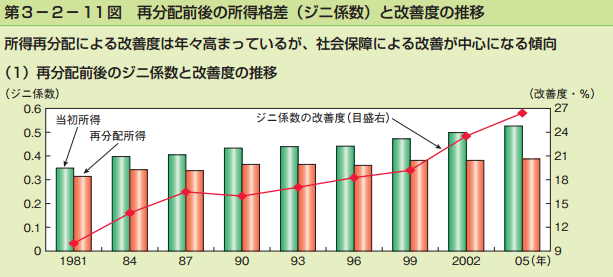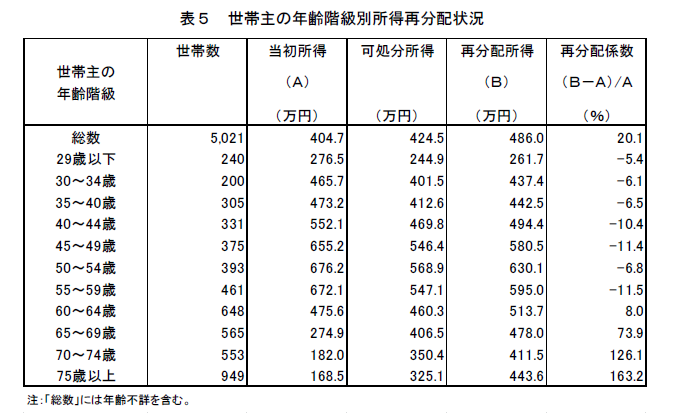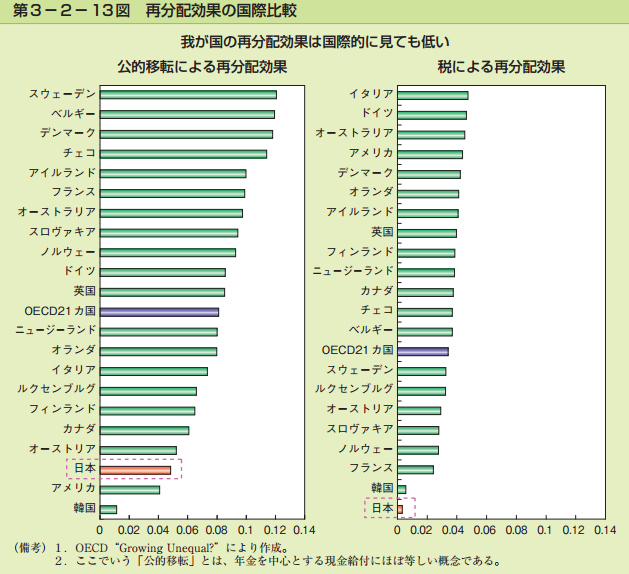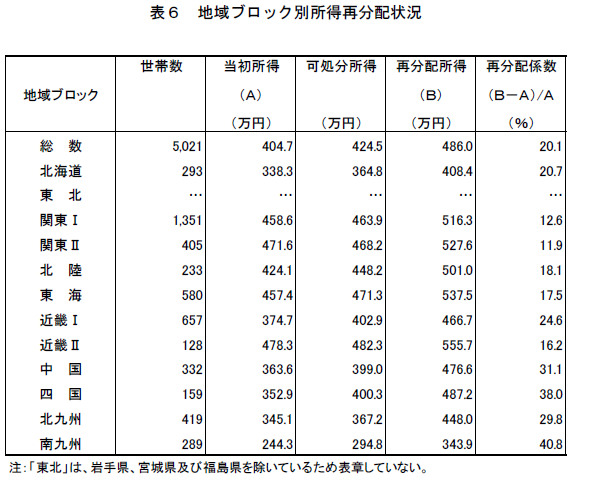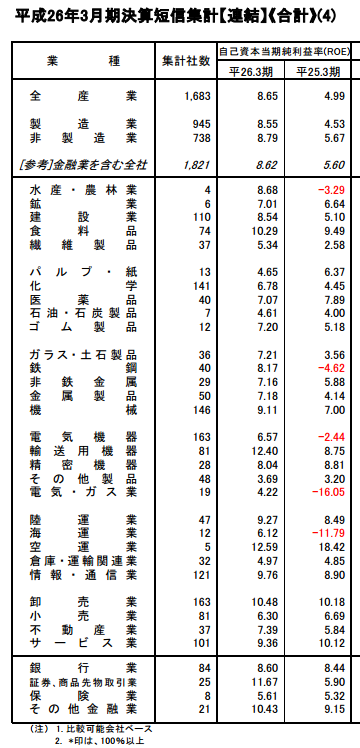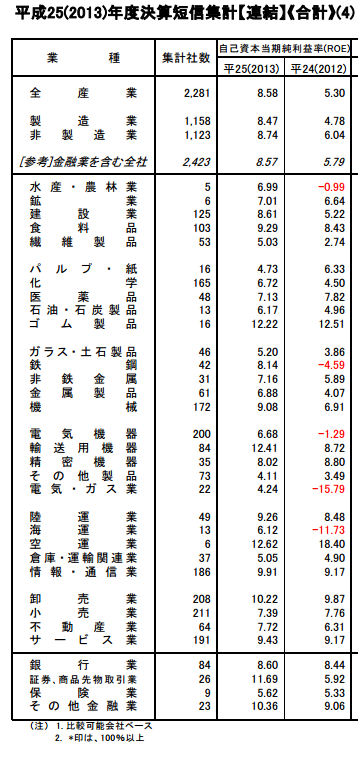あなたが10年かけて身につけたものが割り箸を綺麗に割る程度の技能だとしても挫けてはならない。どうせ能力の消費期限は年々短くなっていっている。あなた自信をアップデートすればよいだけだ。
学習・訓練することへの投資が重要であることに疑いを挟む余地はない。得られる成果に個人差はあれど、どのような分野であっても効果が見込める数少ない万能のアプローチである。
輪転印刷機などの印刷機械が発明された18〜19世紀に大幅な出版コストの改善があり、本の価格がさがったことで図書館がつくられ、そして世界中に大学がつくられるようになった。20世紀終わりにはインターネットが発明され、インターネットは印刷に次ぐ規模の情報流通コストを下げる革命となった。まだ大学を継ぐような高等教育方法はでてきていない。moocなどいくつもの試みがなされている段ではあるが、そう遠くないうちに、学習と訓練の投資効率を格段にあげてくれる方法が確立するだろう。
人材価値を無視することへの疑問
ピケティの21世紀の資本では人材価値が最初から考慮外においている。「実物資本がなくて人的資本に意味があるんですか」「人的資本は物理資本にも反映されているのだ」というエクスキューズは無理筋なのではないか。
人の価値は企業価値会計にこそ乗ってこないが現在の企業評価上は重要な位置をしめる。中の人たちが欲しいからとチームを買い上げるために企業買収などがなされることがあるのに、そこの経済的価値をまるっきり考慮外におくのは変な話しだ。
例えば教育というコンテンツだけをみても、そこをとりまく物的資本がソフトウエア的な価値を内包していたり、比例しているとは考えられない。フランスなんて「のれん代」を企業資産として計上できる制度会計であったように記憶している。ブランドを価値評価できる国で人材のような無形資産についてかくも無碍にあつかってよいものか。
能力の比較優位
デヴィッド・リカードの比較生産費説なるものがある。例えば、農業国家と工業国家があれば、それぞれの得意に集中し生産したほうが、自由貿易下では互いにより高品質で多くの財を享受できるというものだ。
投入できる資源・労働力が同じであれば互いの得意なところで分担したほうが結果がよりよいものになるというのは、国よりももっと小さな法人レベルの組織でも言えるし、家庭のような最小単位でも言うことができる。労働生産が可能な複数人が参加する社会において、よりよい未来をつくろうと協力しあうのであれば、その人物は他の人物と比較して優位な部分を分担しあうのがよい。
社会はゲーム理論でいうところの非協力ゲームではないので、そのうちにその比較優位が機能するところに均衡するものと期待できるのではあるが、均衡するためには十分な繰り返しがなされなければならない。だが、個人の人生という単位でみれば根幹からの職業変更をするような機会は少なく、日本では雇用自体も非流動的であるために不適合、不合理なまま世代が終わるということはままあることである。
また個人よりも法人組織のほうが収益力も成長力も上であるので、個人の能力の比較優位の組み合わせよりも法人間の生産能力の比較優位が優先される。個人能力の比較優位が「声が大きい程度」でも、組織内政治を繰り返し非協力ゲームをしかければ能力の優位性での競争も潰すことができる。その組織の全体の生産能力を食いつぶすまでは・・・。
そのために協力ゲームのなかに嘘つきで人を喰う人狼が混じった非協力ゲームが繰り広げられることもあり、人材価値を一意的に推算することを困難にする。
能力の所在価値
プログラミングができるという能力について考えてみよう。
平均的な能力の人がプログラミングを書いたら1秒かかる処理があるとする。
とある人物はそれを0.8秒で終わらせることができるとする。
この人物は他の人に比べるとプログラミング能力というものについて絶対優位を持っているといえる。
だがしかし、処理がわずか0.2秒早くなったところで、それそのものだけで経済的価値を生み出すことは困難である。
だが、プログラミングというのは反復継続するのが得意なので、たとえばそのプログラムをもってある工場の製造工場の制御部分に導入したとすると、一秒あたりの製造効率がざくっと25%も増えるわけだ。いくつものラインで導入されれ製造数が数万、数十万という数に登れば莫大な時間削減、コスト削減、製造能力の増加になる。あるべきところに能力を置くと、経済価値を生むという例である。
だがしかし、プログラムのような複製が容易であるものの場合、社会に必要なのは1つだけである。
0.8秒のものが登場した次点で、多くの1秒のプログラムしか作れない人はお払い箱になり、そして0.8秒の人も0.7秒でつくれる人が出た次点でお払い箱になる。IT業界ではこのようにある日突然価値が無くなることをサドンデス(突然死)とよんだりする。自動機織り機が出た時代、自動車が出た時代のような新陳代謝が恐ろしいスピードで行われているのである。
ITは距離的優位性というタガがまっさきに外れた業界である。程度の差こそあれ、情報化の影響をうけない産業はないので、今後同じような流れは他の産業にも波及していくものと考えられる。
比較優位と所在価値はますます重要なものになるものになるだろう。そして、個人の振る舞いとして陳腐化の波にのみこまれないためには教育、学習が唯一といっていい解決方法である。
つづく
[財福主義]タグでまとめてます。
このシリーズも、あと2回ぐらいでおわれるかなー
もうすこしわかりやすく、面白くかける才能が欲しい。
21世紀の資本論からの参照箇所等
P327
カッツとゴールディン 高等教育と訓練への投資の明確な重要性
大学教育へのアクセスを拡大する政策は長い目で見れば必要不可欠
しかし1980年以降の米国における最上位所得の急上昇については限定的な効果しかもたなかった
・大卒と高卒以下の所得格差の増大
・TOP1%、さらに0.1% エリート校で学び続けたものに対する報酬の急増
P436
18世紀に比べ、明らかに教育がずっと重要な役割を果たす
でもだからといって社会が能力主義的になったことにはならない。
国民所得の中で、労働に対して払われるシェアが実際に増えたわけではない
人的資本の譲渡は常に金融資本や不動産の譲渡に比べ複雑なため相続財産の終焉が公正な社会を生み出したという考えの確信につながっている
参考引用など
ピケティ『21 世紀の資本』FAQ (v.1.4) 2014 年 12 月 山形浩生
http://cruel.org/candybox/pikettyjapaneseFAQ.pdf