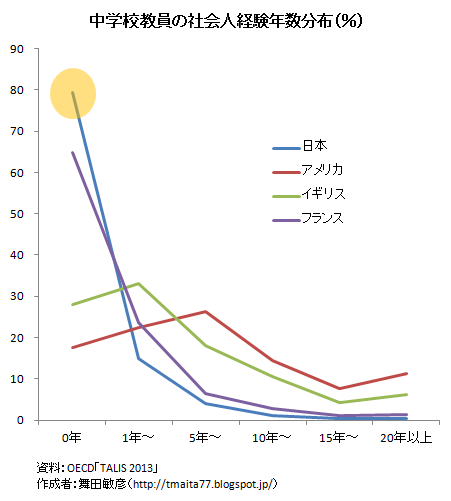空き家について書こうと思ったのだけど、そもそも税についての理解がないと話しもできないのでそっちを書いてたら、そのまま終わってしまった。なので、そこらへんについてはみなさんご存知の体ということで、こんどこそ空き家について書く!
→前段
http://kuippa.com/blog/2014/07/19/%E4%B8%8D%E5%90%88%E7%90%86%E3%81%AA%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E3%81%A8%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E5%BB%83%E5%B1%8B/
三鷹市の安心安全課の方が言うには、空き家の定義は難しいそうだ。
他人が見て、これは誰がどう見ても空き家だろう!といっても、法的な所有者が「いや年に1回は使ってる」「使うかもしれない」と言えば、それを空き家とするのは途端に難しくなる。電気のメーターの契約状況などの証拠を積み重ね、ようやくそれを空き家だと判定するが、別荘のように家屋をいくつも持っている人は居るし、例えば海外転勤などで長期家を留守にする人もいる。
制度上、権利者の居ない家というのは無い。しかし所有者が自分がその権利を持っていると気がついてないことはある。
持ち主が死んで相続が確定しないまま法定相続人が増え続ける土地と家屋。朽ちる家屋はより朽ちた制度の上ではよりわかりやすく顕在化する。莫大な資産であれば相続人も眼の色を変えるかもしれないが、逆に負担が発生するような場合、朽ちた家の義務を問われても撤去などの費用をどのように負担をするのかで合意形成は難しい。親から子、さらに孫、ひ孫、玄孫と、延々と権利者がネズミ算的に増えていくことで当事者間に面識もなくなり連絡も難しくなる。
空き家で伸び放題になった樹木。電線に絡まる蔦。崩れて飛んでくる屋根。
しかし、行政などの公がその木を切ろうとしても、そこには権利の持ち物であるので、行政執行手続きを取らない限り撤去もできない。他人の樹木を傷つければ器物損壊だ。
三鷹市のデータを引用する。
一戸建て件数 28,651
空き家数 617 (2.15%)
老朽度高 80
老朽度中 161
老朽度低 376
これら空き家の持ち主を苦労して特定して連絡しアンケートをとったそうだ。
「維持管理で困っていること」
管理の手間が大変 21
管理を頼める人がいない 5
維持管理の委託料が高い 2
特にない 32
その他 8
未回答 6
なんと、特にないが一番多いのである。
「住宅の賃貸」
賃貸する予定はない 55.4%
現在、賃貸の検討おwしている 13.5%
将来的には、賃貸したい 8.1%
その他 20.3%
未回答 2.7%
賃貸する予定もない!
つまるところ、放置しているから空き家なのであって、放置してて困ることありますか?ってたずねたところで、別にないよねというところなのだ。なにせ空き家にしておいたほうが経済的には合理性が高いのだ。
ついでに、三鷹市の商店街の空き店舗状況についても引用しておく。
1900店舗中、158件の空き店舗、テナント募集されているのはうち34店、されていないのは124店舗。貸そうともしていないわけっす。まあそのなかの一店舗はうちなんだけど。。。だから大変なんだって。貸したり弄ったりすると……。
昨日こんなニュースがあった。
池袋の空き家に住み62歳男逮捕、カセットコンロで自炊
http://www.hochi.co.jp/topics/20140718-OHT1T50046.html
東京・池袋の住宅街にある50代の女性が所有する空き家に、2週間住みついていたとして、警視庁池袋署が住居侵入などの疑いで住所不定、無職の袴田清臣容疑者(62)を現行犯逮捕
(略)
一戸建ての平屋で、6年前に女性が両親をひきとってから空き家となった。家の中は普段散らかっていたが、袴田容疑者が不要な衣類などをごみの日に捨てていて、きれいになっていた。袴田容疑者はこれまで池袋周辺の公園などで生活していて、取り調べに対し「これからは充実した生活が始まると思った」と話している。
空き家から発生する、ゴミ屋敷化、スラム化、失火の確率、倒壊などによる被害可能性、ネズミなどのペスト。
放置は社会的コストは増えるが権利者のコストは減る。
日本の住宅地は細かく細断されあちらこちらに家が建った。集合住宅も多く建った。100年住宅だのなんだのと言われているが30年落ちの団地の解体すらもままならない現状で、いったい誰がそのコストと負担するのかは重要なポイント。
放置することによる経済的メリットは、その物件価値をVとすると
(V*0.8)-(3000+600*x)
0.8:小規模宅地控除
x:法定相続人数
3000,600:基礎控除
すくなくともこれ以上の価値がないとだめ。
解体もしくはリノベートするイニシャルコストをIvとして、
それらを運用することで得られる利益率をまあ30年償却ぐらいで考えると、
Iv/30
ここから建設コストを算出できるぐらいの浮く分がないとやる価値がない。
不動産についてはおおよそ受託金利での借り入れになるので、本来であればその資金運用で得られたお金を耐久消費財へ固定しているわけで、その機会損失分も考慮にいれる。この金利分も運用コストにのせなければいけないだろう。
最近の利益率の下がっている日本の産業構造下で、30年先の建物物件への投資コストと借り入れ分金利まで読み切った上でアクション。これって蛮勇じゃね?
この将来にわたる得られうる利益は、もっとも利潤が得られる合理的な動きを人がするという前提であれば、将来価値Fvの現在価値Pvは少なくとも多くの不動産所有者については合理性ないよね。
利益率をr%と考えればn年後にV円として計算されるような物件の現在価値なんて、ざくーっと考えても
Pv=V*1/(1+r)^n
でしょ?
日本は新築で建てた瞬間に半額になる世界なんだから、税の問題刺し抜いても現在価値低すぎる。これで利益出せるってかなり条件に恵まれてるかタイミングがいいか、お花畑思想しないと踏み出せないよね。
不動産がもっとも安定的に運用できるといっても、人口動態推計を考えれば数十年もしないうちに労働人口1/2になるのに、10年型落ちの物件の将来価値考えれば放置がベストウエイになることはポートフォリオ上、十二分にありうる。
すくなくとも保守費用と利益をバランスさせるためには潤沢なフローと相当な工夫が必要。フローでどうしょうもないから、相続のために資産を借金でバランスするみたいな条件でもないかぎり……。んー。
ちょっと暴走しすぎたかな。多分誰もついてこない気がする。まあいいや。ここらへんは問題点として共有できない気がするし。
日本で最も安全に運用できる新発国債10年ものの金利はわずか0.54%、0.0054だよ!
リスクフリーレートが0.54%のところで、リスク取りに行って勝負なんてしかけてもコツコツ稼いで大きく負けるよね。
だって何もしないという行動選択肢は利益も0だけどリスクも0なんだもん。
http://www.sankeibiz.jp/business/news/140705/bsd1407050500009-n1.htm
空き家問題に詳しい富士通総研の米山秀隆上席主任研究員は「住宅ローン減税などで、新築よりも中古を買ったほうが手厚くなるようにするなど、金銭的な後押しがあると効果的だ」
メリットがないならペナルティでコントロールしよう。みたいな世界じゃでぇ。
「ふふふ!ご褒美にムチ打ちの回数を少なくしてやろう!!」ってなってくると、
「何もしないのがもっとも合理的だ」みたいな、合理的な判断に寄っているだけだと思うんだよね。
「働いたら負け」みたいなNEET思想もそりゃ流行るわ。
働いたら罰金 →所得税
買ったら罰金 →消費税
持ったら罰金 →固定資産税
住んだら罰金 →住民税
飲んだら罰金 →酒税
吸ったら罰金 →タバコ税
乗ったら罰金 →自動車税・ガソリン税
入ったら罰金 →入浴税
起業したら罰金 →法人税
死んだら罰金 →相続税
継いでも罰金 →相続税
上げたら罰金 →贈与税
貰っても罰金 →贈与税
生きてるだけで罰金 →住民税
若いと罰金 →年金
老けても罰金 →介護保険料
老いたら罰金 →後期高齢者働かなかったら賞金 →生活保護
まあ、これはこれでどうかとは思うけどさ。わからなくもないよ。
負のフィードバック係数の方が大きすぎて現実そうなってると判断されてもやむない。
特に税金なんて持っているもの、稼いだものの割合、%で累進でかかってくるから、稼ぎが大きかったり、持っているものがおおきかったりする人のほうが影響がでかい。稼げる人や資産家がリスクをとるより何もしないほうが合理的だとなれば、防衛のために働かない、何もしないなんてのも選択されうるよね。
例えばせっかく空き家問題をなんとかしようと一棟買い上げのシェアハウスが増えてきたところに、一時期シェアハウスは寄宿舎扱いして建築基準をあげたり、寮母を置かないとみたいな競争阻害、新規参入阻害条項を設けたでしょ。
確かに脱法シェアハウスのような蜂の巣みたいなところに人間ぶっこんで人権的にアウトなんじゃないかというような、ものは問題だけれども、将来価値がゼロどころかマイナスにしかならないような網かけたらそりゃ破壊的成長なんて、ありえないわ。セキュリティと利便性は相反するので、制度決めるひとはきちんと将来フローまで考えて施策をうってくれないと困ってしまいます。
特に土地に自重自縛されてる地縛霊みたいな資産家は、防衛戦しかできないんよ。だってコツコツ稼いだぐらいじゃ焼け石に水ぐらいの石のうえで焼き石土下座強要されるようなもんだし、どうせぇっちゅう話なんじゃないかな。そりゃ動産を持ってる人はこれだけ流動性たかければ海外で回すよね。海外で製造して日本で売る。結果、国内に産業も育たないし、雇用も生まれない。アベノミクスで株価があがったいってたけど海外経由からの投資寄与率6割とかじゃなかった?細かい数字わすれたけど。うん。64%、6割でいいや。
将来価値を無視して、単年度予算、ショートタームでしか考えないのはつくづくダメだと思う。壊しては建てを繰り返し蓄積しない。価値が育まれないし育たない。今後10年ますます顕在化する空き家問題。20年後の空きビルの維持費用、解体費用、50年後の空き超高層ビルの維持費用、解体費用。どーすんのよと。耐久消費財は作成時だけでなく、維持解体にも資金が掛かる。道路やトンネルでも同じこと。権利と義務の所在はふわふわーっとしたまま。
空き家問題は象徴で、試金石。
空家等対策法をつくるべく準備しているらしいけど、単なる補助と控除事業に終わらないことを期待したいです。
◇補助対象
地方公共団体が行う次の事業
・不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却
・除却を行う者に対する経費補助(地方公共団体の民間に対する補助)
・空き家住宅又は空き建築物の活用
・活用を行う者に対する経費補助(地方公共団体の民間に対する補助)
・所有者の特定◇国費率
・不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却 ・・・2/5
・除却を行う者に対する経費補助(地方公共団体の民間に対する補助) ・・・2/5 ※5
・空き家住宅又は空き建築物の活用 ・・・1/2
・活用を行う者に対する経費補助(地方公共団体の民間に対する補助) ・・・1/3※5
・所有者の特定・・・1/2http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000011.html
うん。もろめっちゃ控除と補助だった!
所有者の特定とかもうしなくていいんじゃないかな…
放置認定して管理委託を自治体が引き受けてその費用を権利者が払わなければ、公知手続き後、その費用徴として競売ってな感じで。
活用事業は結局なんだかわからないNPOが跋扈する補助金じゃなくて、ゴールを設定して達成型したら報奨金とかにしようぜ。しようぜ。しようぜ…。
空き家をリノベートして売上、利益、雇用の評価の上位に報奨金合計1000万円!とか。これくらいなら民間団体でもアワード設定できそうだね。
誰かやらない?やって。やって。
シェアハウスとかカフェ縛りとかでもいいからさー
**参考
国土交通省 空き家再生等推進事業について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000011.html
「空き家」激増…全国で利活用が拡大 シェアハウス転用、バンク後押し (1/4ページ)
http://www.sankeibiz.jp/business/news/140705/bsd1407050500009-n1.htm
一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会 空家住宅情報
http://www.sumikae-nichiikikyoju.net/akiya/
【シェアハウスの『寄宿舎』扱い→規制緩和】
【号外】<シェアハウス>寄宿舎並み規制を撤回へ 国交省
http://www.sharehouse180.net/archives/520
東京証券取引所 投資部門別売買状況(株券/CB)
http://www.tse.or.jp/market/data/sector/