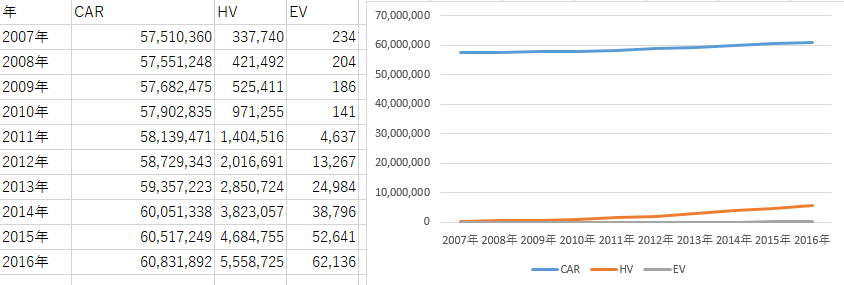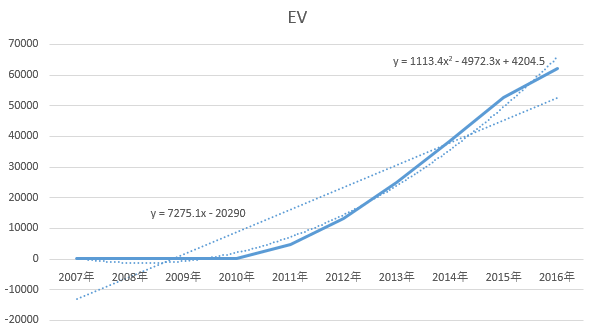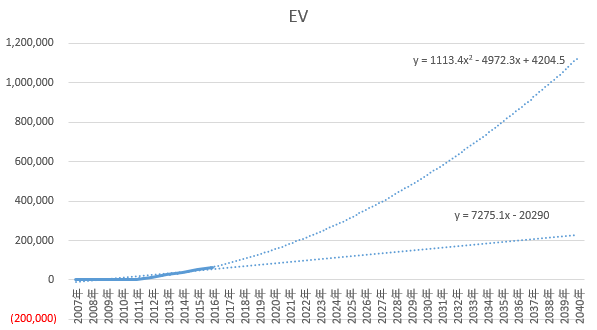ヴォイニッチ手稿がまたもや解読されたという。こないだのロシアに数学者につづいて今度は、イギリスの中世の文献の専門家だそうな。ちょっと英語圏の動向を追ってみたけど、ラテン語の人たちが「お前まじでか」と言っているようなので、残念オチかもしれない。興味があったので英語の報道ほうを読んでみたけど、ちと自分にはわからなかった。2行しかないのかね?
ヴォイニッチ手稿の解読ついに成功?そこには婦人病の治療法が描かれていた!?(英研究者)
http://karapaia.com/archives/52245622.html
ロシアの数学者たちが「ヴォイニッチ手稿の言語構成の解読に成功」との報道。使われている言語の60%は英語とドイツ語であることが判明。そして内容の一部には「ケシからアヘンを採取する方法論」が含まれる模様
http://indeep.jp/russian-mathematicians-proved-the-meaning-of-the-voynich-manuscript/
なんかロシアの数学者達のほうが、まだアプローチがちゃんとしてる感。
ラテン語と古ギリシャ語
日本人がその語の成り立ちを考えたときに漢文の影響を排除できないように、英語も古典ギリシャ語やラテン語を無視することはできない。e.g. (exempli gratia / たとえば)、化学や自然科学領域では死語とされているラテン語でさえもそれほど遠くない存在で、いまだそこここにある。
化学科の大学一年生は有機化学などでIUPAC命名法を習うが、きちんと命名法に従って記述されていれば化学式を連想することができる。ここで主につかわれるのは元素記号や学名がラテン語に由来していて、冠でギリシャ数詞がもちいられる。古ギリシャ語やラテン語のくびきからは現代社会でも効いている。
略語で意味を通じさせることができるのは、共有知、暗黙知があればこそである。
ちょいと古いがネットスラングで、afk(away from keybord)だの、wktk(ワクワクテカテカ)などがあるが、ゲーマーがタイプ速度を優先したのと、墓石などに刻むのに母音が落ちる方向に省力化されてきたのもの似たようなものかもしれない。
IUPAC命名法でいうところの2-プロパノールが慣用名イソプロピルアルコールで通じるのは、その双方で単語の背景に知っておくべき知識が暗黙的に共有されているからなのさ。
読まれるための文章と読まれないための文章
常用されていないのに、略語を使う理由は読まれないための工夫だと思われる。
はたしてヴォイニッチ手稿は読まれることを前提としたものか、読まれないために工夫したものなのか。
同じようにまだ解読されていないレヒニッツ写本などは、右から左にかかれている以外は素直なので読まれることを前提としているものだと思うが、正直ヴォイニッチ手稿はどちらなのか判別できない。
ラテン略語でかかれたのであれば、後人にも読まれるための文章として書かれたものであろう。しかし、それが、それがページセンテンスごとに意味を持つには、略語だとしてもページあたりの語彙数があまりに少ないと感じるのだ。表音文字であればなおさらである。exempli gratiaをe.g.と大胆にサイン化、表意化したとしても、その情報量は少なさは補えないんじゃなかろうか。
もし、これらが読まれないための工夫がされていた場合、それは暗号ということになるが、暗号であればさらに複号前の語より情報が落ちるのが常である。日本語のような表意文字の情報の圧縮度に比べたら大した情報を含んでいないじゃねぇかな。
個人的には文章のようにみえるものはただの文字楽譜だとおもうので、奏者にだけわかればよい、後人にも読み方さえ教えてあげれば読めるものとして残したのだと思うが・・・・・・、そういう個人的主張はおいておいて、仮にヴォイニッチ手稿に意味ある文章が略記されているパターンを考えてみる。
暗号と複号
暗号文より複合文のほうが情報が多くなるパターンを考えてみる。
「今日の5限の体育本当にめんどくさい。」という文意を伝えた女子高生同士のメモのやり取りが発掘されたとして、そのメモが「次・授業・だるい」としか書かれていなければ、欠落した「体育」という情報にたどり着くのは不可能に近いが、メモの共有者同士では、次の授業が体育であると暗黙的共有があるので、意思疎通ができる。
そのような、暗黙知をテキスト化して、暗号表にする方式がある。
事前に配っておいたスパイ手帳の3ページ目4番目の項目を実行しなさいとかを指示するだけであれば、北朝鮮工作員御用達の乱数放送みたいに数字をラジオ放送で流すだけで意思疎通ができるうえ、相手は複号用の鍵を手にいれるまでは推測でしか暗号を読むことはできない。
複号用のテキストに聖書のようなポピュラーな書籍を使うこともあるが、センテンスでの引用ができなくなるので、単語ごとの引用になる。この場合は、ほとんど暗号文と複合文のテキスト長はかわらなくなる。
125ページの3行目3番目の単語(P125L3W3)、32ページの12行目5番目の単語(P32L12W5)のように、羅列する。P45L12,P21L3W1,P21L4W4 のようになり、ヴォイニッチ手稿は異様な繰り返しの多さ、まるで音楽のシンコペーションのような特徴をみたしているので、可能性として、なくもないかもしれないけれど、年代からいっても「鍵の本」が失われているので、複号は無理だろうね。
単語の出現頻度などから推測はすることぐらいしかできない。まあ、その場合は、完全に読ませないための工夫がなされた暗号ということになるね。
まぁ、でもなぁ
突然だけど、
武具、馬具、ぶぐ、ばぐ、三ぶぐばぐ、合わせて武具、馬具、六ぶぐばぐ。
菊、栗、きく、くり、三菊栗、合わせて菊、栗、六菊栗。
これは、1718年より上演されている有名な歌舞伎演目の外郎売の一節。もし、これにまつわる、いろいろなものがロストして、ふいに、この文面だけ後世に伝わった場合、日本語の単語こそ使われてはいるが、そこから意味をすくい取るのは困難であろう。武具、馬具、ぶぐ、ばぐなんだから、2武具馬具なんじゃないかとか後世の研究者を悩ませるに違いない。
パイポパイポパイポのシューリンガン
シューリンガンのグーリンダイ
グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの長久命の長助
ここまでくると、もっと研究者を悩ませることになるだろう。落語の寿限無は既に発生年代不明になっているようで、米沢彦八(~1714)より後っぽいが、まあ、そんな感じ。
カエルピョコピョコミピョコピョコ。
https://youtu.be/qo_Ihn6PCuE
ドリフの早口ことばとかを聞きながらおもうんだけど、やっぱり文字譜なんじゃないのぉ。あってもチャントぐらいだなぁ。シンコペーションの効いた繰り返しが多すぎるよ。
ちなみにイラストのほうには意味があるのは同意。
昔のこのブログ投稿。
線をひけばすぐわかるヴォイニッチ手稿のイラスト
ヴォイニッチ手稿に書かれたスペイン語
ヴォイニッチ手稿はどうみても楽譜
c.f.
有機化学論文のラテン語
http://chemistry4410.seesaa.net/article/135191973.html
ギリシャ語及びラテン語の数詞
http://www.nihongo.com/aaa/chigaku/suugaku/greek.htm
学術用語におけるラテン語の影響についての研究
http://ci.nii.ac.jp/naid/120005578685
IUPAC命名法
https://ja.wikipedia.org/wiki/IUPAC%E5%91%BD%E5%90%8D%E6%B3%95
学名
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E5%90%8D
外郎売
http://www.arcadia-enter.com/geiko-pro/school/04.html