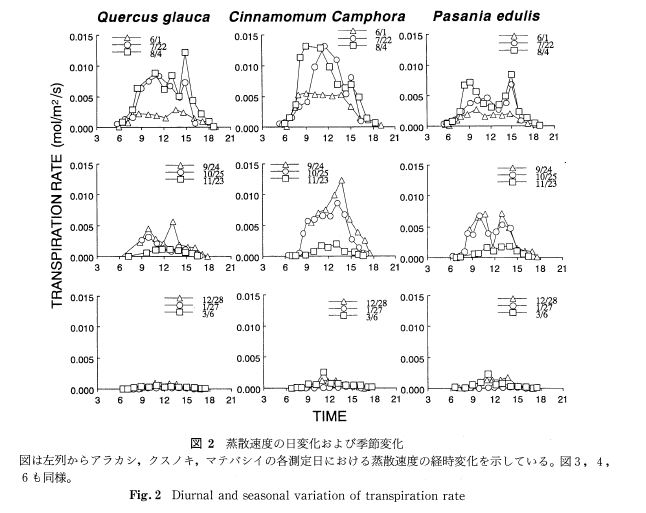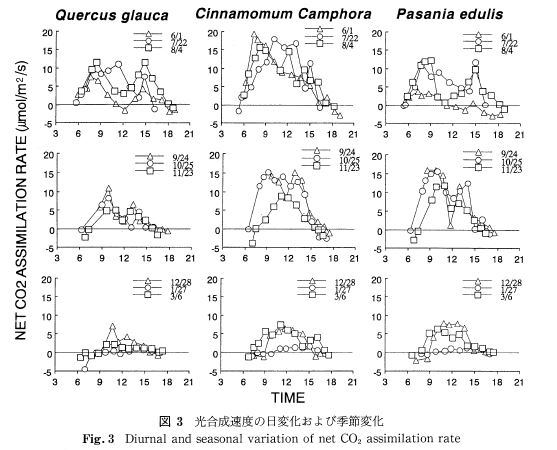ルノー、三菱自動車、三菱自動車工業の会長であったカルロス・ゴーンが東京地検特捜部により身柄を拘束された。これについての報道や世間の反応をみていると、この国では無実と無罪の区別について思考放棄がすすんでるのかなとか感じたりもする。株式上場している会社について憶測を交えていいかげんなことを書くと風説の流布になってしまうので、あまり踏み込んだで書きたくないのだが、外形的なことを私的ブログでぐだぐだ言うぐらなら許されるだろう。
海外ドラマと海外法律
いつの間にか契約していたAmazon Primeで、BGMのように海外ドラマやらアニメなんかを流している。今は海外版の「suits」をシーズン6までみてるところ。もう最終盤。ドラマではハーバード・ロー・スクール卒業と弁護士を騙るニセものだけど天才と、実績も才能もあるけれども勝ちのみにこだわる冷血漢な師弟コンビが繰り広げるドラマなんだけれども、こういう海外ドラマを多く見すぎたせいか、今回の事もお国の事情が違うだけのことのようにもみえてしまう。法律や常識は国ごとに大きく違う。
事実か事実でないかに違いがあるように、事実であってもそれが罪を構成するかは全く別のものである。日本で16歳がタバコやお酒を飲んだら犯罪になってしまうが、英国では16歳から可能なので高校にバーがあったりする。カナダなんかは先日、大麻が合法となった。ところがかわれば常識も法律も違う。
罪刑法定主義
独裁国家でも国民情緒法でもなく、罪刑法定主義を採用している近代国家は法律に明記していることが罪と規定される。法律にかかれていないことや、法が制定される前の事柄について罪に問うことはできない。法の不遡及の原則。これが法治国家だ。
日本は憲法はもちろんのこと法律のアップデートも著しく遅い国であり、商法の改正なんかは120年ぶりだそうな。120年前にはインターネットも携帯電話どころか固定電話も怪しいわけで、その時代に考えられたものを骨組みを弄らないまま増築と継ぎ接ぎだけでなんとかここまでやってきた。
裁判官が法の趣旨を斟酌して下した判例法とも揶揄されるものが逮捕や起訴の根拠になることはあっても、まぁ、それでも罪刑法定主義の原則はかわらない。
法体系には主には2種類あって、やってだめなことを規定するブラックリスト方式の英米法系と、やっていいことを規定するホワイトリスト方式の大陸法系がある。日本は大陸法系。
日本からなかなかイノベーションがおきないと言っているのも当たり前で、ホワイトリスト方式の法体系下で新しい技術ができたところで、ありもしないものを法が想定しているわけがない。許認可方式ではノーベル賞ぐらいの実績でさえも立法化までの道のりは険しく長い。
ホワイトリスト方式下で新しいことをやると、だいたいどこかが何某かの法に触れることになるので、罪を構成してしまう。今では当たり前になったWEBの検索エンジンですら著作物のフェアユースがない日本では著作権法に触れるので、最初の頃は国内にサーバーを置くと運営者が逮捕されるとか、技術だけでなくそういう回避行為を同時に考えなければならなかった。
だが、そんなようなことを法で規定するためには「USBの穴が穴でなにするがそんなことは部下に任せるので知らん」って人とポートとジャックの区別も怪しい人が議論ができるぐらいまでに基準や前例が必要となる。だから、ある程度技術が枯れてからじゃないと議論もできない。
アメリカとかは提訴大国だが、やらしてみて駄目だったら懲罰的損害賠償をあたえて手打ちにしようっていう考え方なので、新しいことも事故もばんばんおきる。他方、従前的なやりかたを続けていれば、大きな変化もないが、逆に大きく間違えもしない。どちらにも一長一短がある。その良し悪しはここではおいておくことにして、同じ民主主義国家でも国が違えば法律も罪もその構成も異なるって話。
ごびゅう、誤謬性
で、そのホワイトスト方式の日本では刑事裁判の起訴後有罪率は99.9%だそうだ。ダブルバインド、二律背反したような法律が日本にはいくつもあるので、起訴までいっちゃえば何某かの罪に問うことは容易で、こういうことになるのだと思う。ギルティとノット・ギルティが正規分布すると考えると、犯罪認知後の無罪の偏差値は80以上ってことになるが、おい、おい。
工業生産などの現場では不良品がないかをチェックするとき複数段階のチェックを置く。
このときのチェックががばがばでもきつきつでも生産効率は悪くなる。エラー検定率(第一種過誤)は通常、5%とか1%で設定されるそうだ。全体の20%をハジクようなチェックや、100%通してしまうようなものはチェック項目として間違っているのだ。
この有罪率の高さを見ると事前にふるいにかけているのだろうが、有罪にするものとしないものを担当者がアンダーデスクで振り分けるって、あー、それ、人治だよね?
司法取引
司法取引は早く導入されるべき制度だと思っていたのだけれども、まだ2回めだそうな。さすがに驚くほど未成熟ですな。なんだいこれ?やばみ!
ヤクザの親分による殺人示唆と実行犯による殺人で、親分捉えたいがために実行犯をみのがして親分だけ狙うみたいな話しのように見えるよ。まあそれもありなのかもしれないけど、「suits」風に言えば、検察と内部通報者による共謀で悪意訴追ととられてもおかしくないよね。悪意訴追なんて法律日本にはないけど・・・。
もし100億の報酬を、50億に見せかけてた金融商品取引法違反って話しが本当なら、利益を得たのは会長かもしれないけれども、実行犯は故意を持って行動した経理やIRであり、それを監査する監査法人や弁護士には通報義務を放棄したことになるし、なにより善良な管理者の注意義務がある取締役はなにしてたんだって話しだよね?ここでどんな関与と罪の減免の司法取引をクローズドにしたまま、これは司法取引ですって、ちょっとかなり乱暴すぎない?なんで被害者側に立ってるの?君たちもまず捕まったうえで司法取引はなされるべきじゃない?
犯罪構成要件
ちょぼちょぼ情報のリークがあって内容が二転三転しているのが気に入らない。
最初逮捕された当初、過少申告による脱税かなとかおもわれたが、カルロス・ゴーンは日本に月の1/3も居住していないことから、申告地が日本にないことがわかると金融商品取引法で記載が義務付けられているIRの虚偽記載となった。売上の粉飾ならともかく、役員報酬の虚偽告知であるという。それで会長が逮捕!?証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがあるってことか???
だがこれも報道を聞いているとなにか要領を得ない。
現在のところ、どうも、会長職退任時に約束していた退職金の50億を報酬としてIRに載せろってことのようだ。金銭の授受に基づかない発生主義に則った退職給付引当金みたいなもんだろうか?まあ、いわんとすることは、わからなくもない。まあ、そんなもんが特損に乗ってたら投資家は逆に混乱すんだろ。
どうなるんだろう?貸借では固定負債について、損益では特損?キャッシュフローは動かないのか?わかんねぇな。この場合、わかる人のほうが少なそうだけど。もうちょっと詳しく事情がわかるようになったら誰か解説してほしい。
私的流用と投資
日産本体ではなく、海外子会社経由との報道もある。もうこうなるとわけわからん。
日本とフランスは国際租税条約を結んでいると思うので、主な在地がフランスであれば、フランスでの申告になろう。でも、フランス経由のオランダとかそういうタックスヘイブンのペーパーカンパニーを経由された所得だったりすると、日本側でなんかできることあるの?それで連結の虚偽記載においたの?その出資金は預け資産じゃなくて法人持ち株としての出資?財務活動のほうじゃなくて?
ブラジルの次期大統領選に出馬とかが噂されてたりするけど、主がブラジルだったりすると、日本とブラジルだと、犯罪者引き渡し条約すら結んでなかったよね?これだともっと厳しくなるよね。立件まで継続できるんだろうか?国際問題になるよね。間違いなく。
私的流用。
日本の不動産は新築の物件が買った瞬間に二次流通では半額になるが、これは世界では稀有な例で諸外国では異なる。特にゴーン氏が家族を住まわせたとされる、ブラジルやレバノンのような国では、年に4〜7%のインフレがあるので現金で所有するよりモノで持ったほうが価値が毀損しないどころか、10年も寝かすだけで倍値になる。都市部ではさらに値上がりが見込めよう。
その上、世界的に有名なカルロス・ゴーンが住んでいたというプレミアムが付けば、さらに高値で売ることができるだろう。海外住宅は家具はもちろんのこと冷蔵庫洗濯機、食器やスプーン・フォークまで住宅についていたりする。家族を住まわせていた、いつでも住めるようになっている、という事実と、それがまるごと売り物だという事実はなんら背反しない。
浪費や流用と投資の区別は、成果を見れば一目瞭然だろうが、不動産についてはちゃんと言い訳ができそうだ。コーポレートベンチャーキャピタルとか投資会社が民間投資しねぇで不動産ばかり買っているっていう非難はできるかもしれんが、投資会社が逆に財産の管理および運用とかを定款とかにいれてないのだとしたら、それは一体なんの会社だい?
家族旅行とかベルサイユ宮殿とかはどうだろう。これは正直よくわからない。
ただsuitu脳だと、コーポレートカードでそんなもの買ったりそんな贈り物だとかのお金の使い方して経費って認められるのか。恐ろしいなアメリカっていう日本とは違う常識の国があるのも確かだ。
財閥や華族が解体された日本では、放蕩なのは成金ぐらいだが、欧州のビッグファミリーとか王族とかと付き合うためのビジネス上の必要経費とすれば、庶民感覚ではないところで、妥当な必要経費なのかもしれない。100億、日本の自動車会社のトップとしてはもらいすぎの額でもアメリカ自動車産業と比べれば、それでも少ないそうなのだ。
民意と感情
理論では納得できても、感情で納得できないという話しはよくあることだ。
コストカッターで知られるってことは、多くのリストラをおこなったってことで、当然恨まれてもいる。
50億もらってるひとがさらに50億ちょろまかしてた、家族旅行で数千万つかってったっていう報道を聞いて、妬み嫉みから自由でいられるほどの寛容性をさすがに多くの日本人は持ち合わせていない。
だが、それを利用して誘導し煽っているようにも見える。それが今回眉間にシワがよるところだ。
でも、それが本当に罪を構成するのかは、感情に流されずに判断できるようになりたい。推定無罪なのに解任になる日産と、推定無罪で解任にならないルノー。ここに答えがあるようにも思える。
疑わしきは被告人の利益に。・・・なってないね?
手続き
FBIとかが逮捕のときに読み上げるミランダ・ルールにある「あなたは弁護士の立会いを求める権利がある!」が、日本にそんなものはない。弁護人はつけられても取り調べのときに立ち会わせることはできない。取り調べの可視化もされてなくて、録画も全体の1%程度と十分でない。そんでまた今回の共謀っぷりがぷんぷんの司法取引。悪意訴追を追求する制度もないし、警察内部に監察官みたいな部門はあっても、検察を捜査するような独立性の高い組織は日本にはない。検察審査会制度で申し立てがせいぜいだ。ちょっとだめかなと思う。江戸時代は北町と南町で輪番制が機能していたが、今のような、シングルスレッドの司法警察行政はフォールトトレラントじゃない気がする。
電撃不意打ちでルノー、日産、三菱自動車の会長を逮捕拘束したが、カルロス・ゴーンのような経済上の大物を捕まえて、もしこれが誤認逮捕だったとしても、刑事補償法上の補償内容は、一日で最大12,500円にしか請求できない。最大でだ。系列の工場勤務の派遣従業員でさえもっと大きな経済被害が出るだろう。ゴーン逮捕でどれほどの経済損失が生まれただろうか?インパクト50億どころじゃない気がする。
もし内部通報者のクーデターの為に、検察が共謀したのだとしてもそれを問うことができる仕組みは日本にあるだろうか?誤認逮捕とかで、うっかり死刑にしても最大で3,000万円にしかならない。刑事補償法はノータイムで改定したほうがいい。あと120年かかるかもしれないが、やったほうがいい。
ゴーンぐらいの大物相手でも代用監獄収容を繰り返すのだろうか?
我々は我々のやりかたになれすぎて違いに気が付けない。海外からも大きく注目される事件なので、こいうのでもきっかけでちょっとづつにでもよくなるといいね。
再びsuits
ジェシカは男子トイレでの喧嘩をなんでいつも仲裁できるのだろうか、不思議だ。なんでも織田裕二版のテレビドラマもあるんだとか。ハーバード・ロースクールの偽弁護士を最終盤、追い詰める証券取引委員会の調査員にショーン・ケイヒルが重要人物で登場するのだが、この役は誰がやるのだろうか? ぜひ。…to …. you!
参考
https://www.nikkei.com/news/image-article/?R_FLG=0&ad=DSXMZO3813554023112018EA2001&dc=1&ng=DGXMZO38135510T21C18A1EA2000&z=20181124
「ゴーン後継」巡り綱引き 日仏連合、成長戦略に暗雲
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38135510T21C18A1EA2000/
https://www.youtube.com/watch?v=dIiEHpodoHs
日本の刑事裁判の起訴後有罪率99.9%は本当か?検察の捜査力について
https://izumi-keiji.jp/column/jiken-bengo/yuzai-99-per
第一種過誤と第二種過誤
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%A8%AE%E9%81%8E%E8%AA%A4%E3%81%A8%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%A8%AE%E9%81%8E%E8%AA%A4