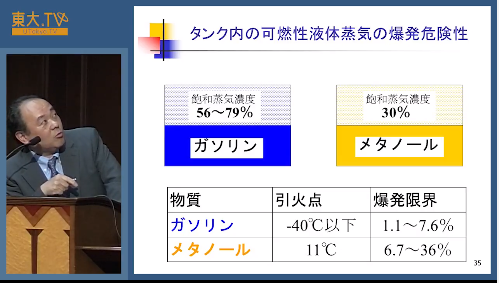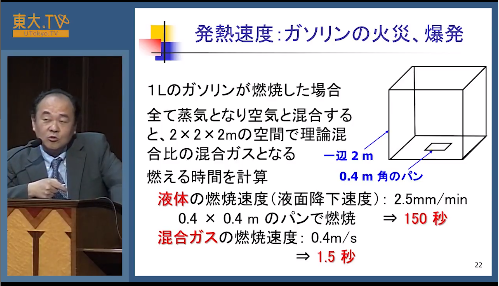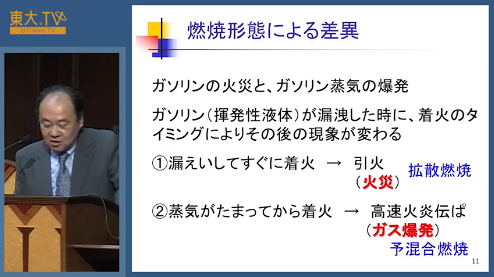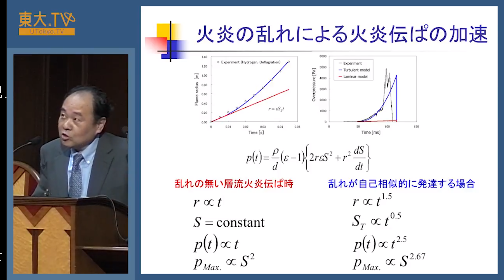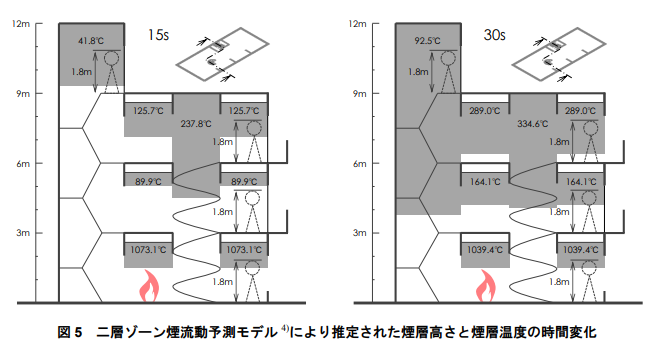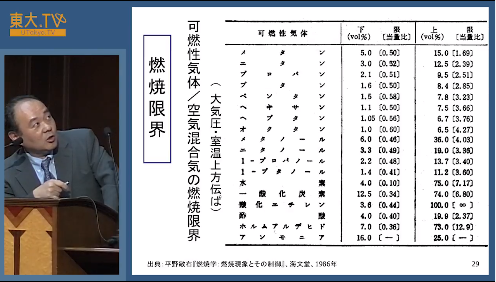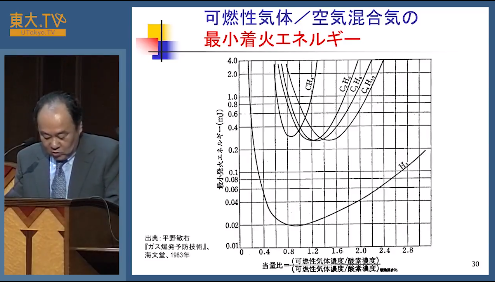10月22日は「即位礼正殿の儀」が行われた。令和。
「昭和天皇の即位のときの飾りは兄弟で担当して袖のボタンはわしがつくった」と、戦前金細工だった爺様が言っておったけれども、なにぶん子供のときにきいた爺さまの話しなのでその真実も今では知る由もない。袖のボタンってことは洋装だろうし、御列の儀かな?
先日閉幕した愛知トリエンナーレでは、その昭和天皇の写真と背中に和彫入れ墨を入れた尻出してるヌード写真とコラージュし、異国語のような民謡にのせてバーナーで燃やし、それを足で踏みつけて灰をにじるという映像作品の一部がネットで拡散して大炎上した。
全編を見もせずに批判するなという意見があり、20分ほどの全編がyoutubeでも公開されているというので、どれどれと思って見てみたら、断片で見たときよりもことさらにひどく、こりゃ良い子や年寄りにはみせられねぇや・・・と思った。
表現の不自由がテーマで、図録が焼却処分されたことなどエクスキューズされていたが屁理屈にもならない。
自由という権利の行使には結果が伴うし、その自由の行使の責任からも自由になるわけではない。中には憲法21条を持ち出して「表現の自由」を叫ぶ意見もあるが、ならばイの1番、憲法1条1項をなぜ読み飛ばすのだろうか。
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」とある。「俺はみとめねぇ!!」と反体制精神を見せるのもいいが、国と国民を全方位にまとめて腐さしたらそりゃ少なからず誰かが怒ったり悲しんだりするのは当たり前ではないか?
他人の譲れない部分の信義や信条を攻撃したのなら反撃をうける。私はあなたのことが嫌いですと言って、でも、それを伝えた相手の意見は聞くつもりもない。「私は傷ついた。」という感想を持つ人に、法では禁じられていないとか、これは表現の自由だといふことに意味あるか?
世の中には色々な考えを持つ人がいるし信義信条を異にする人もいる。極端なことを言えばソシオパス、反社会性パーソナリティ障害の人もいる。すべての人の価値観、意見や感想が一致することなどはありえない。神奈川のやまゆり園障害者施設殺傷事件の犯人は、もっと社会的賛同が得られるものだと持論を皆述したように猟奇殺人犯や大量殺人犯でさえも彼らなりの言い分はある。
例えば共産主義や社会主義のように貧富の差や身分差のすべてを無くしたいという政治的思想を持つひとにとって、天皇皇室は認めがたいものであろうし、他宗教を熱心に信望するものにとっても、無意識的忌避の対象となりうるだろう。
心情を言ったり伝えたりすることは自由だ。行動に移せば責任を問われる。それだけだ。
表現の自由はある。
正直、これらの表現の不自由展で展示された作品をいくらつくろうが、わたしは問題はないと思っている。他人に迷惑をかけない範囲で好きにやればよろしい。あぁ、そういう主張をもった人達の作品なのねと思うぐらいだ。今回の作品群のなかで言えばChim↑Pomの作品は被災地の若者たちの心の叫びを演出なしで捉えたのだとしたら、なかなかに捉えがたい一瞬を捉えたものだと思う。岡本太郎の明日への神話へのいたずらは、褒めることはできないが、あのタイミングであれをやれたことは評価している。
だが、一作家が物議を醸す作品を表現したところで、今回のように誰も彼もこんなにヘイトを稼いだりはしなかっただろう。
裏切られたパブリックトラスト
いかんだろうと思うのは、今回は意図を持って作品を選択し、集め、できるだけ多くの人に見せようと努力をし実行した主体に公が絡んでいたことに大きな原因がある。
トヨタのような日本有数の大企業や、地方自治体行政、県政、はたまた国が公金をぶっこんで、このようなアレンジをしたらそりゃ、ものすごいヘイトが集まる。
テレビなどの報道では平和の少女像(aka 慰安婦像)が騒動の原因として、名古屋市河村たかし市長の座り込みも「日本国民に問う!陛下への侮辱を許すのか!」と書かれたプラカードは映さない徹底ぶりだそうだが、そりゃそうだ。皇室がらみとなれば多く年寄りにはいまだ単なる敬慕の念以上のものを持つ人達も少なくない。国内放送法の放送コードに耐えれても、老人ばかりが見るテレビで年寄りの心臓が耐えられないだろう。
教義が異なれば、異教徒の首を切って衆目に晒す主張を正義とすることもあるし、略奪して持ってきた死体を博物館に並べたり、積んだ骨を模様に並び替えて入場料をとったりする。市中引き回しのうえ打首獄門とか、河原にさらし首とか、広場に集まってみんなでギロチンを見るために集まるとか、奴隷を競技場で死ぬまで戦わせるとか、相手の生首を互いのバスケット状のリングに入れる試合とか・・・あげればきりがないほど、国や時代が変わればいまでは信じられないようなことも実際におこなわれてきた。
大英博物館にいけば他国から略奪してきたミイラが並んでいる。これはいうなれば死体展示である。教会の屋内で何気なく足元をみると、そこは墓石の上だったりする。あちらでは寄付金を多く積むといいところに埋めてもらえる。壁にミイラ状態で置いてある人さえ居る。ヨーロッパのあちらこちらでは骸骨堂を見ることができるだろう。模様状に並べられた頭蓋骨、お花模様に並べた大腿骨や肩甲骨。綺麗でしょと言わんばかりの観光スポットだ。
現代から見れば信じられないが、当時の人たちはありえるものだと思っていることは多くある。
これが保っているのは文化というコードだ。
文化というコードを揃えるために、宗教がもたらした影響は大きい。
神道の場合は道徳形成というよりは、古神道が担ってきた役割を考えると農芸化学や建築などの技能伝播と評するのが近いような気がするが、それでも、広域の現代日本人の社会風習に通底するところに神社などの文化風習が根付いている。その神社の祭司のトップが天皇であることも間違いないなくて、検証委員会で自分はキリスト教徒で天皇にまつわる作品を作ったと言う作者(小泉明郎氏 空気#1)もいたけど、宗教を掲げて宗教をディスるって危うさしかないよね。
補助金
公金が手続きなしに止められたのは表現の自由に反するだの、補助金適正化法だの住民監査請求からの議会で追求していくべきだの賛否両方から揉めている。
だけど、商店街の活動費を得るために2/3助成5万円とか10万円の補助金で、申請書かいて、予算案つくって、計画書提出して、審査会でプレゼンして、結果報告書書いて、実績報告会で報告して、領収書とか様式整えて、交付の通知を得るまで一年かけたりしてるのを実務として長年担当していると、俺のこの時間別のことで働かせてくれぇぁしあああ!!と思う。企画の内容が実施されなかったら、補助金なんかもらえないし、なんか事務的にしくじれば、返えせ!とか言われることも実際聞く。
別の町会が年寄りばかりになってしまって、街路灯を維持できなくなったので辞めたいと自治体に相談したら、街路灯を作るときに出した補助金を返すことなるぞとか脅されてひーひー言いながら維持したりしているなんて話しも聞く。引くも地獄進むも地獄。
なのに予算総額12億のイベントのほうがこんないい加減なんだなと思うとやるせない。美術館をつくるっていう仕事に噛んでみたくて、いっちょがみして少し見聞きしてみたんだけど、学芸員さんとかの経済的にひーひー言ってる世界を垣間見るに、なんとも陰鬱とした気持ちになる。なんなんだねこれは。
他国の政府の影響力工作や、特定の政治的主義主張のため、他の宗教からの他の宗教への特定方向へのディスリスペクト。これをアートという文脈に乗っけて公金で運営するって、そりゃヘイト集めるわ。
俗習、文化という暗黙的な不文律の中で我々は生活をしている。
そんなことはやらないほうがいいよと、法令や条令で行動を予め明文化しなければいけない社会など歓迎したくない。
アートには奇抜さや過激さだけではなく、熟達した技芸を競うことも忘れないでほしい。今日の儀をみて細部まで凝らされた服飾や高御座などに使われている色の発色などの技の極みをみて、つくづくそう感じた。
参考
憲法1条1項は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」
憲法21条1項は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」
あいトリ「燃やされた天皇の肖像」「放射能最高!」を批判するなら知っておきたいこと | 文春オンライン
https://bunshun.jp/articles/-/14837
「表現の不自由展」中止問題 検証委や出展作家らがフォーラムを開催(2019年9月21日)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2141&v=-p14VEv11T0