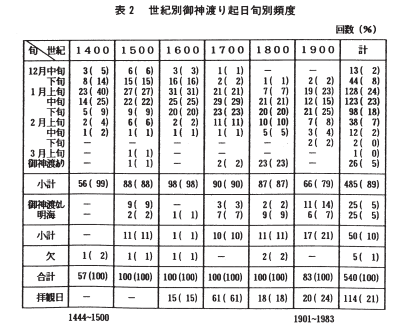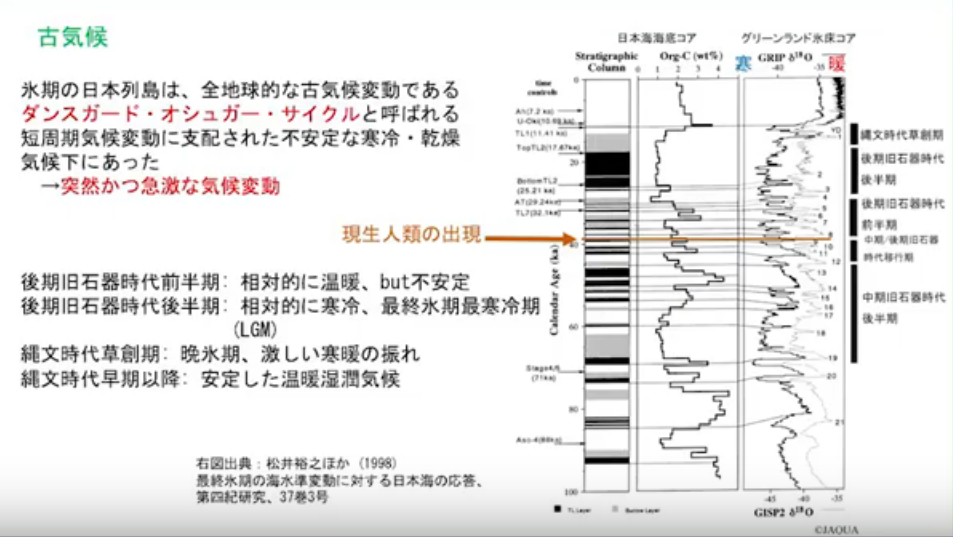海外で新型コロナウイルスの感染症対策として、「挨拶としての握手、ハグやキスもやめよう。」という周知がなされている。
握手をしない、ハグやキスをしない。
それって元来の日本風ですよね。
握手ではなくお辞儀をする。
おそらくだけれども、お辞儀が挨拶の主流のアジア圏は過去にひどい感染症が流行ったのではないか。
動物が行うキスやハグは相手との細菌交換の助けになるので、結果として免疫をあげることに寄与する。 類人猿などのコミュニティがそうするように、生まれたばかりの赤子が免疫を獲得するために母子がそうするように、本来はこちらが自然な形なのだろう。
だが、なぜかフィジカルコンタクトをしない文化圏が生まれる。
類人猿はもともとはお酒を分解する酵素をもっている。
果物などの糖を含むものが腐る(発酵する)と酒、そして、酢になるので、冬場の食物が少ない時代を生き抜けるように、もともとはアルコールを分解する能力があるのだ。
アルコール中毒にみられるように、脳みそも糖で動く回路と酢酸回路がある。飢餓状態になると、酢酸回路に切り替わりなかなかもとに戻せなくなるのだ。
だがアジア人の大半はウワバミと呼ばれる人以外はお酒に酔うし、そして何割かは下戸だ。アルコールをアルデヒドに分解できず、またアルデヒドを酢酸に分解する酵素を生成する能力もたないない。
長江周辺で米作りと伴に分岐したと思われるこれらの人類グループはある種の熱帯域特有の感染症を本来は毒物でしかなかったアルデヒド(二日酔いで頭ががんがんするあれね)を利用して、防いだのではないかと言われている。
ここで日本の文化を振り返ってみる。
お米によって作られる、お酒、日本酒というのは酒造りのなかでもかなり特殊な製造方法によってつくられる。
でんぷんを糖化する過程と、糖をアルコールに醸造する過程、さらにはできあがったアルコールに火入れして発酵を止めるなどの工程がある。これら3つがひとつの醸造の過程でおこなわれるのは日本酒だけだという。ちょっと不正確。わすれた。
でんぷんを糖に分解することは、麹菌をみつけるまでは人間の唾液に含まれる酵素を利用しおこなってきた。(口噛み酒)
酒、酢、そのほかにも味噌、醤油、納豆、糠味噌、粕漬け、鰹節をつくるためにカビを利用するなど、日本はこれら微生物を利用した発酵については、いまでも世界に類を見ない多様性をもった文化圏である。詳しくは「もやしもん」でも読んで。
酒造り杜氏はお酒づくりの期間は納豆を食べられないという。
体についた納豆菌が麹菌に勝ってしまって、お酒にならないのだそうな。
菌をいじる界隈にはコンタミネーションという言葉がある。目的の菌以外による汚染のことで、酒造りもコンタミをしてしまうとお米もお酒にはならずただ腐るだけになってしまう。
日本には防疫の概念がないというが、醸造や発酵で目に見えない世界があることを知っていた日本人は、それについての振る舞いをいくつもつくった。
人間は古い時代から病気になってきた。
外的理由によってその原因を類型すると、寄生虫によるもの、カビなどによるもの、病原菌によるもの、ウイルスによるものがあげられる。
穢(けがれ)とはつまるところコンタミだ。ウイルス感染。宿主がウイルスに侵された場合、生物汚濁状態になり、その穢れは伝染る。 ヒトヒト感染する病気の場合は穢が再生産されることと同義だ。
これを防ぐには禊(みそぎ)、水浴により身を清めることだが、まあ、綺麗にしなればならない。
寄生虫であれば煙であぶったり、日に当てて紫外線にさらしたり、火で清めたり、髪の毛をエアシャワーで払うように、大幣で祓ったり、まあ様々あるけれども、やり方さえ間違えなければ現代の化学でも似たようなことをやる。
忌み(いみ)というものは、「死・産・血などの汚れに触れた人が一定期間、神の祀(まつ)りや他人から遠ざかること」ということになっているが、まあ、ていのよい隔離だ。忌みの人は人混みにいくんじゃねぇよと。公共交通機関の利用は控えてくださいみたいなことだ。
現代でも監察医はもっとも未知の感染症にかかりやすい職業であるが、専門教育も専門知識もなかった時代はなにやら伝染る目に見えないものは、人から遠ざけて隔離するよりなかった。
動物の死骸、皮なめしなどをするひとが差別された時代があるが、衛生環境がよくなかった時代では、動物の死骸から寄生虫だけでなく、肝炎ウイルスやその他の病因源となった。専業従事者は低暴露をうけているのでいずれかの段階で抗体をもち無症状であるが、これが抗体をもたない人と接触してしまうと劇症化してしまうことがある。
知識もなかった時代の人たちが隔離というわかりやすい策で身を守るのも、まあ、やむないことだ。それが現代まで続くのは違うとおもうが。
神道ばかりをみたが、仏教はこれら死についてはもっと踏み込んでノウハウがあるようにみえる。坊主が来ている袈裟はウコン染めだが、うこん染めは殺菌効果ばつぐんだ。
死体処理についての、ノウハウの塊といっていい。
初七日や49日、回忌など、火葬の前の土葬の時代は、埋めた死体を掘り起こして、お骨にして再埋葬するなどという手間が必要であった。ここらへんも踏み込んだら多分すごいおもしろいんだろうけど文字数とおれの知識不足。
やがて末法の世ということで、なんでそうやっているのかもわからず様式だけを真似る世になる。
烏帽子をかぶり頭髪をみせないのが最低限のマナーであった時代がかつての日本にあったように、やがてマスクをせずに唇を見せたりすることが激しく礼儀違反とされる時代がくるかもしれない。
家に入る前にスギ花粉を落とすように、肩を払うのがそのうち儀礼様式化する時代がくるかもしれない。
あ、そうそう、ちょっと計算してみたところ、スギ花粉ひとつにはコロナウイルスが2700万個ほど入るようだ。スギ花粉でひーひーいってるひとたちがマスクで立ち向かう姿は勇ましい、まあなんだ、そんなヒステリックにならずに。喧伝におどらされないようにしてね。