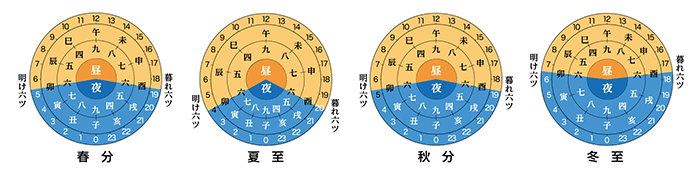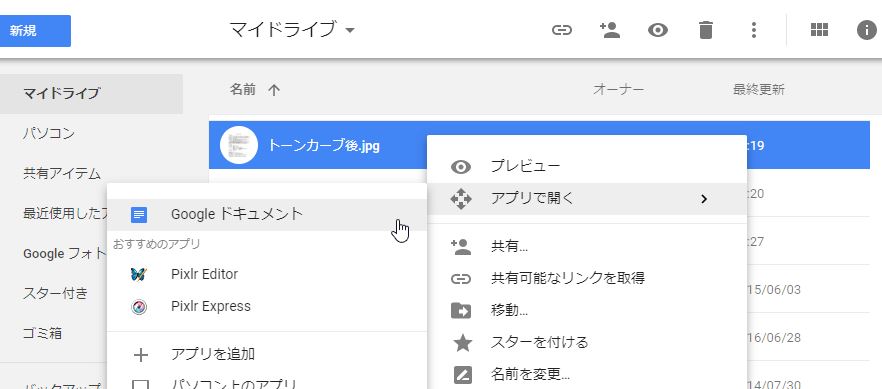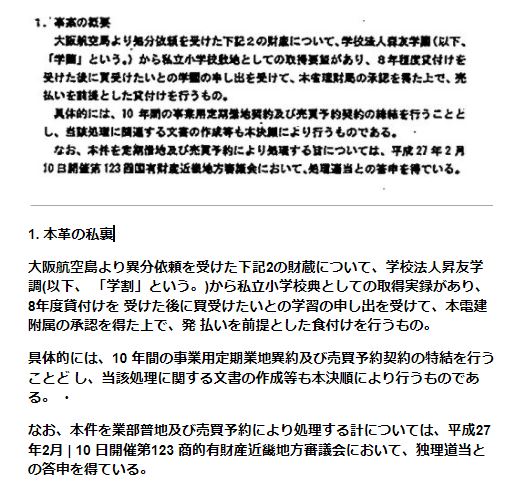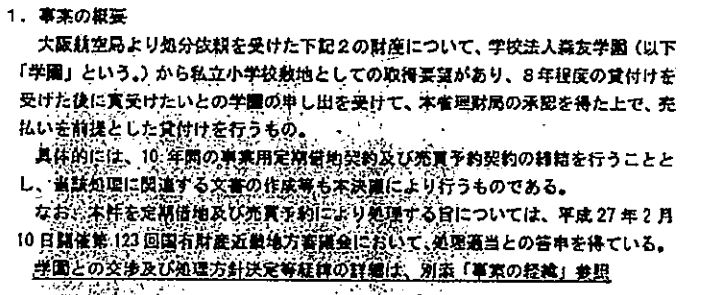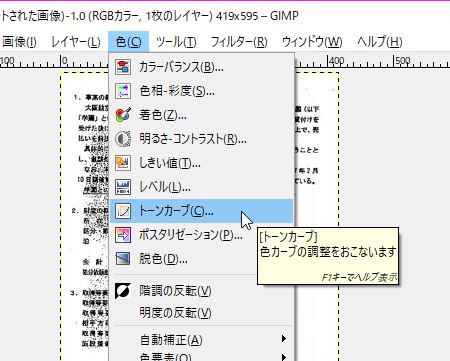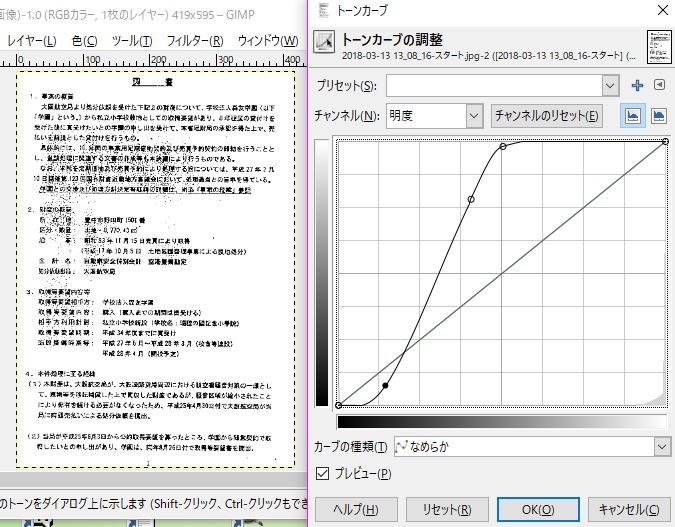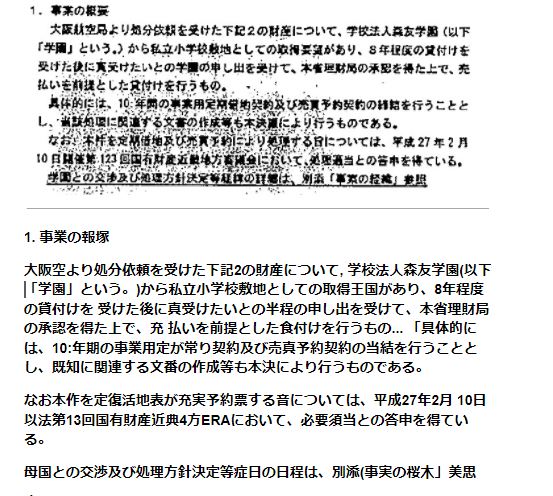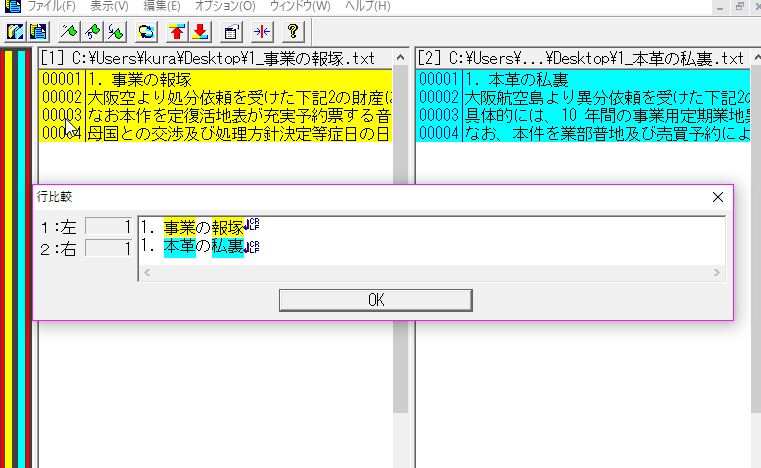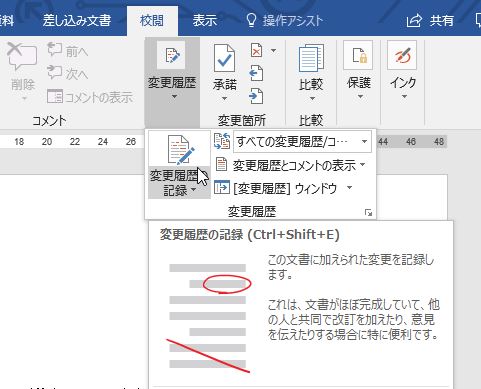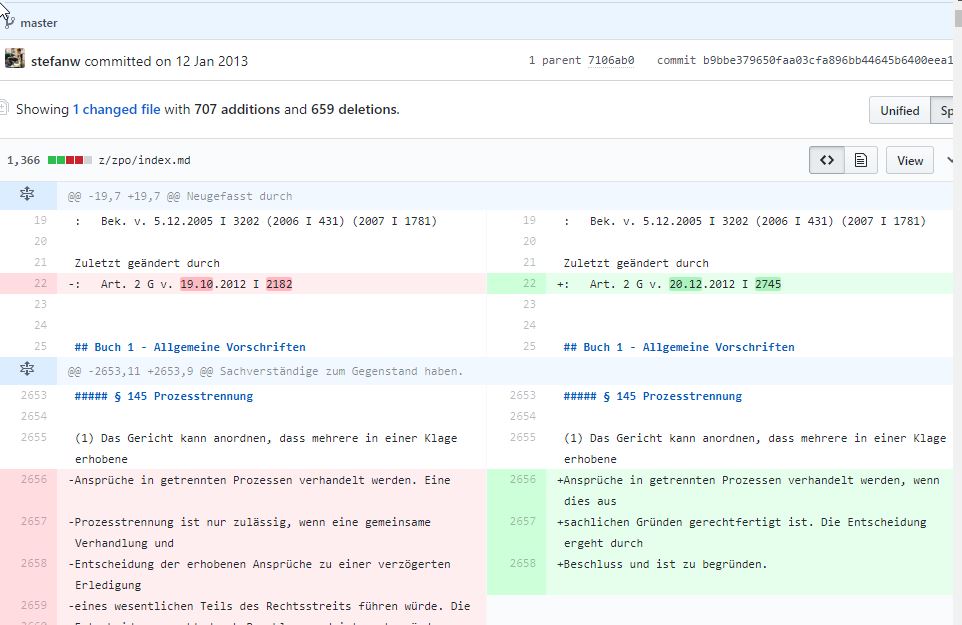平成最後の夏期講習と題し、落合陽一氏、小泉進次郎氏の企画で、政策と技術であれこれ社会課題を解決しようというような大人の夏期講習がおこなわれたようだ。いろんな分野の人たちが5分程度のライトニングトークをして、それぞれテーマにわかれた島でディスカッションして最後に議論をまとめて発表するというような形式で、動画配信している。
ポリティカル×テクノロジーでPoliTechだそうで、議論のしかたも今どきだし、いいねと思ったでのピックアップ。全体の様子およびガイダンス、講義・インプットおよびガイダンスはこちらで見れる。
- ●ヤフー株式会社CSO 安宅和人 我が国の未来に向けたリソース投下の現状と課題
- ●株式会社メディヴァ代表取締役社長 大石佳能子 人生100年の幸せな老後
- ●メディアアーティスト 落合陽一 今後10 年でやってくるテクノロジーの転換点
- ●株式会社Campus for H共同創業者、予防医学研究者 石川善樹 社会保障のオリジン
- ●一般社団法人WITH ALS代表 武藤将胤 障がいと向き合う事で、生まれるイノベーショ
各テーブルごとの議論はこちらから。
https://www.youtube.com/channel/UCcQ5QML9wkc-hj8aWEf-NYA/videos
各位の議論はおいておいて、それぞれのテーマごとにせっかくなので、自分なりにポリテックについて考えてみたいと思う。今回はAの島のスポーツと健康について。
まとめテンプレ
- 今までの分野の課題
- 今後の分野の課題
- 問題解決の指針(何をどうしたら)
- ポリ(政策的に解決するには)
- テック(技術的に解決するには)
- その分野の未来ビジョン
A:スポーツ健康島
2018/7/31 第一回平成最後の夏期講習(社会科編)
テーブルA<スポーツ・健康>
「なんのための健康・スポーツか?― Well-beingという視点」
★株式会社Campus for H 共同創業者・予防医学研究者 石川善樹
・東京慈恵会医科大学 総合医科学研究センター先端医療情報技術研究部准教授 高尾洋之
・公益社団法人日本フェンシング協会 会長 太田雄貴
・株式会社Deportare Partners代表取締役 為末大
・国土交通省 総合政策局政策課 政策企画官 喜多功彦
・サイボウズ・ラボ主幹研究員/東京工業大学特定准教授/一般社団法人未踏理事 西尾泰和
議論ピックアップ
スポーツとエクセサイズをわけたほうがいい
スポーツが社会参画の一助になっている
イギリス、公園管理者には植物の専門家だけでなく、スポーツマネージャーがいる
海外では公衆衛生法の中に公園があるところがある
予防医学は病院で見れない
病院は病気しか見ない、健康を見れない
e-sports 対戦相手が必ずいるから寂しくない
今までのスポーツ健康の課題
スポーツや健康がいまだに根性論に支配された精神論であること。
科学からいまだ遠い。
疫学的な論理性、客観性、再現性がスポーツ健康分野でも必要。
民間療法がいまだに幅を効かすことができるのは、その余地があるからだ。
今、スポーツ選手のパワハラの問題が話題になっている。オリンピック候補生クラスの子がコーチにビンタされている様子などが動画が出回ったりあちらで会見、こちらで会見などがおこなわれている。指導の姿勢とかそういう以前に公の法律レベルでアウトなことは閉じた世界だからといってやっていいことではない。程度が低すぎて議論の余地もない。
自分が子供の頃、水泳とか陸上とかは学校選抜になる程度に身体的運動能力に恵まれていた。小学生の頃、新潟県に数年間いた。新潟県は縦長なので上中下にわかれてるのだが、そのうちの上越と中越の大会で優勝したことがあるし、国際規格のプールで大会記録や会場記録なんかを持っていた。だが、通っていたスイミングでは中級コースに留まっていた。なんでかっていうと選手コースには絶対にいきたくなかったからだ。
なんで嫌だったかというと、指導とは名ばかりのプールサイドから割れた竹刀で頭を叩くぐらいしか、コミュニケーション・プロトコルをもたないおじさん達しかいなかったからだ。東京から引っ越してきた自分にはかなりのカルチャーショックだった。ここで何か水泳に役に立つ指導をされた記憶はないがこういう大人もいるのかという社会勉強にはなった。中級コースですら何回かはサボっていた。月謝を払って理不尽に堪えるのはなかなかマゾい。
低年齢時におけるスポーツにおける競技成績など、おおよそは年齢に比較した発達ともとよりの生体機能でしかない個体差だと思う。
水を飲むな!休むな!のように、ひたすら追い込んで、生き残ったやつがいい奴だみたいなトレーニング方法があるが、これはトレーニングではない。生存者バイアスと兵卒をふるい分けるときに用いられた新兵訓練方法だ。
第二次世界大戦後、帰還兵に職を斡旋した際これらの訓練方法が野球などのトレーニング方法として取り入れてしまったことが現在までスポ根の悲劇の根底にあるように見える。
知能テストは第一次世界大戦時に、新兵の兵科を決めるためにおこなわれたことをルーツとしている。この知能テストから漏れた新兵の練度をあげ脳筋に仕立てるための「しごき」がフルメタル・ジャケット的なブートキャンプである。
中世時には口減らしの要素もあった戦争だが、近代戦において突撃兵ぐらいにしか役に立たない脳筋はかえって足手まといとなるようになった。戦争よりも高尚なスポーツの世界でならなおさら根性論の運用は辞めるべきであろう。
今の一流のプロスポーツ選手を見ればわかるが、みなさん頭も切れる。例外もあるが・・・。
「小人閑居して不善をなす」のことわざの通り、体力が有り余っている若者にはスポーツでもやらせておけという更生プログラムとしてのスポーツはもう役目を終えたことだと思う。今はなんだ?その役割はスマホゲームとかに任せておけばいいんじゃないかな?
今後のスポーツ健康の課題
最近では遺伝子タイプ別に投薬する抗がん剤を変えたり、遺伝的に速筋と遅筋の割合を調べマラソンに向くのか、短距離に向くのかなどの検査をおこなえるようにもなってきている。
人間は同じように見えて個別に独立した生体であるため、同じことをおこなっても再現性がなかったり、結果や効果効用に差が生まれる。しかし、人間の細胞より人間の腸内にある最近の数のほうが多いぐらいなので、塊りとしての人間はそれほど単純でもない。だから統計的傾向により推論して精度をあげていくよりない。
都合のいい結果が出たデータばかりをチェリーピッキングするのではなく、効果がなかったり、失敗したデータの蓄積こそがこれから重要になっていく。何事にも例外は生まれるが、これの取扱を間違ってしまうと、因果と擬似相関の取扱を間違えてしまうことになる。
成功があるとすれば、それは失敗にかたどられた空白域である。だから失敗の蓄積をいかにしていくかが今後の課題となる。健康分野については成功談などではなく失敗にこそ価値がある。
問題解決の指針(何をどうしたら)
個人を診察したカルテは病院のもので個人の生体に関する情報を日本人はほとんど持っていない。
把握しているのは身長体重血圧、よくってコルステロール値ぐらいなものだ。それも年に一度ぐらい健康診断で測定されて紙に印刷される程度のもので経過観察も困難だし、診察する病院が変われば前年度データへのアクセスも困難になる。正直、高級肉牛ほども人間の健康は管理されていない。
熱心な人は睡眠時間や運動量などを記録したりしているが、不摂生で健康に難がある人ほど健康診断をうけなかったりする。だが、この分野の一律悉皆の強制はやるべきではないので、意識が高い系の人たちだけでも、ライフロギングをできるインフラを整え、データポータビリティを充実させる必要がある。それらのデータが貯まればあとは保険の掛け金など経済要因が調整してくれるだろう。
ポリ(政策的に解決するには)
データポータビリティ権はEUで施行されたGDPR(EU一般データ保護規則)で掲げられている権利だ。
もしかしたら遠くない将来に個人の遺伝情報をフルスキャンできる時代がくるかもしれないが、それを私企業や公的機関がデータ保持の主体となると、自身にまつわる情報ですら自由に動かせなくなる。
農作物、畜産動物などでは遺伝子特許が認められつつある現況において、こと人間、個人の生体情報の所属をその個人ではなくしてしまうと、生存権にも影響がでるだろう。
データポータビリティ権はこれから重要なものとなるが、これをどのように扱うか法制化できるのは政策的な動きだけである。
中国のように個人格付けを中央で管理する統制型社会もありといえばありだが、そちらの方向にいかないのであれば、個人にまつわる情報も個人に帰属する財産として法文化する必要があろう。いずれにしろ検討も指針も決めないという無策は論外である。
テック(技術的に解決するには)
農工大の先生だったかな?
歩行者の様子を画像解析してボーンをつくると、感情などは肩の動きに現れると言った先生が居て、デモ動画を見せられて、あー、ほんとうだーと関心したことがある。
似たような研究に、医師でもわからない初期の認知症は歩行者の足の運びで検出できるとするものもあったように記憶している。警備の分野では不審者検知とか、迷子などの検出精度もあがってきているそうだ。
うちの商店街は防犯カメラを数箇所に設置している。ネットワークに繋がってもいないスタンドアロンで警察がなにか事件があるとはしごに登ってSDカードを取り出したりしているが、機械学習バンザイの時代にちょっともったいないよなとも思う。けれども、権力とか監視社会が嫌いな人も多いのでセンシティブ。
だが、テクニカルな面からだけ見れば、公共空間に設置されたカメラを社会リソースとして利用しない点はない。
今は、個人が保持しているスマートフォンなどのデバイスで、加速度センサーなどをたよりに運動量の測定などをしているが、かなり不正確だ。こういうのは外部のカメラで全景センシングしたほうがいい。
数百メートル離れた防犯カメラ間を何秒で移動したから歩行時速が何秒だとか、酩酊状態であるとか、自律神経に異常兆候がみられるとか、歩行者の姿勢などはウエアラブルなディバイスでは解決できない。
これを国や行政が一元管理してしまうと問題があるので、先に定義しなければいけないのがデータポータビリティ権なのだ。
自分の歩いている姿勢や歩行速度、毎日の表情などのロギングがどこかの誰かのものではなく自分のものになるのであれば、犯罪発生時にしかつかわれない監視カメラなどに別の役割が生まれる。
地域防犯カメラなどのローカルインフラは有事以外意識もされないので、ごく一部の有志の負担者によって維持されているが、データポータビリティがうまく機能すれば平時にも活用できるので、設置維持も進むことだと思う。オンネットワークの防犯カメラなどまだセキュリティ面が難しいが、いずれにしろ無自覚なフリーライドはすくなくできるなくなる。
スポーツ健康の未来ビジョン
けん玉初心者がVRで特訓、9割が現実でも「できた」 驚きのVRゲームが生まれたワケ
重力加速度は人間には制御不能なものであるが、仮想空間でならばコントロールが可能である。
楽器の練習などであれば、ゆっくり弾いて弾けるようになったからだんだんテンポをあげるというようなことができるが、重力に支配されているけん玉やおてだまのようなものは一番簡単なものができないと、そこから修練を積む余地もない。
だが、仮想空間であれば低重力下で反復練習を積んで慣れたのち、だんだん現実の重力に慣らすというようなトレーニングができる。
早く走ったり、泳いだりする感覚を掴むためにゴムで引っ張ったりするトレーニングがある。体操でのバク転なども最初は介助者が支えることで重力の影響を直にうけないように、ゆっくり練習することから始まる。VRやARはこれらの新しい仕組みになりえる。
スポーツ健康の俺未来ビジョン
- 町中カメラ
- 歩行がふらついているのを認知。メールが届く。
- 認知症登録の人が歩いていたら家族に連絡が行く。
- 歩行速度を記録。閲覧可能。
- 歩行速度姿勢などから肉体加齢状況を推計。
- 町中プロジェクションマッピング
- ランニング記録から適切なペースメーカーがARでランナーの前に表示される
- 歩幅が狭く緩慢になっている人に年代別の適切な歩幅を知らせる
- どこでもスポーツ
- アーチェリーや射撃のような専用の施設がないと困難だったものをVRなどで解決
- e-スポーツにフィジカル要素(Virtuix Omni的なもの)
- ポケモンGOが高齢者にも受けてるように、町中でARドラクエなど
- 地域コミュニケーションにゲーミフィケーションを導入。(Xさんが5日見えません。姿を見かけたら声を掛けたらXポイントゲットなど)
今のフィジカルVRはこんな感じになっていたりする。
Virtuix Omni