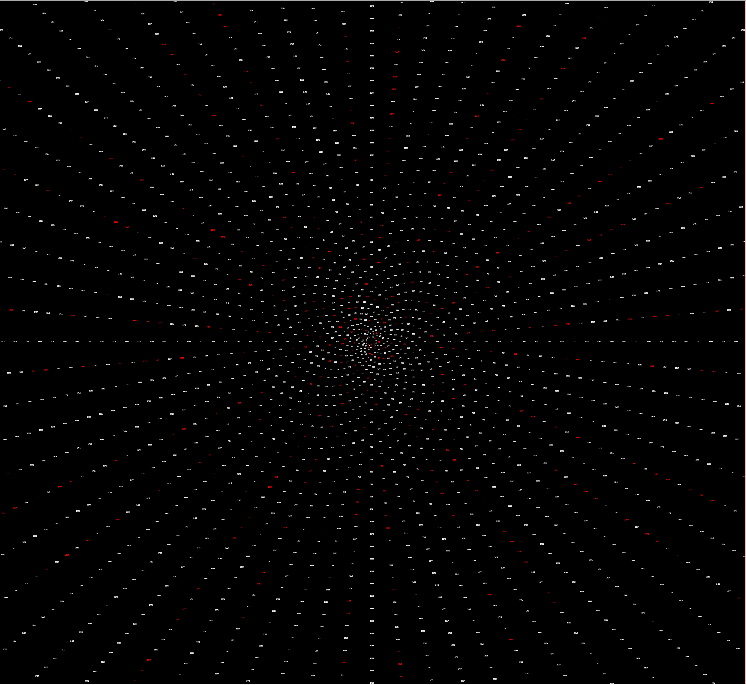Q.結局STAP細胞ってなんなの?
A.細胞が外部からの刺激で多機能性を獲得した細胞。
Q.実在すんの?
A.たぶんしない
Q.実験は続けるべき?
A.実験は続けるべき。
Q.論文めちゃくちゃなのに?
A.論文めちゃくちゃなのに。
小保方さんはSTAP細胞の研究を続けるべきである。
みんなから酷いことも言われてる。着火剤として佐村河内氏による下草炎上があったからなのか、iPS細胞のときの森口氏のあれがあったからなのか、本来不燃物であるものまで炎上してなんか酷いなと思う。科学とは関係ないところに世間の関心があつまり大炎上しとる。
報告の否定(論文がおかしい)
↓
結果の否定(論文にかかれてるデータがおかしい)
↓
実験の否定(実験が正しくおこなわれなかったのでは)
↓
組織の否定(それを監督してた組織はいったいなんだ)
↓
人格の否定(あいつは嘘つきだ、隠れ巨乳の呼び声高い←ふぁっ!?)
全てのレベルがないまぜになって、なんかもうよくわからないけど、今なら叩いても大丈夫的な集合心理が働いていて恐ろしい。科学への冒涜だとか、あいつが犯人だとか、歴史を愚弄しとか、全否定しなければならないだとか、なんだとか。まじかよと思う。
報告書の不備は指摘修正されてしかるべきだとおもう。報告書が否定されたので、しかるに結果が否定されるという判断をする人がいてもよい。
そして、それを本人が形式を訂正することで担保できるのだから、修正したいという意思をもつことはありだとおもうし、それを掲載許可したNatureが、あまりに不適切ということで掲載を取り下げるという判断もありだろう。
だけれども、本人もそれを望んでいないし、Natureも掲載を継続している。しかも誰でもがタダで確認、閲覧、ダウンロードできるようにしてくれている。
Stimulus-triggered fate conversion of somatic cells into pluripotency
http://www.nature.com/nature/journal/v505/n7485/full/nature12968.html
Bidirectional developmental potential in reprogrammed cells with acquired pluripotency
http://www.nature.com/nature/journal/v505/n7485/full/nature12969.html
実験そのものを否定したり、組織を否定したり、あげくにこれを書いたやつは人間的にダメだとか、倫理的に破綻しているだとかそういうことだけを言うべきではないと思う。捏造や報告の形式の否定以上のことをことをするならば、追実験をして、再現できない旨を同じく論文でまとめあげるのが筋なのではないか。ましてやパーソナリティの揶揄や否定は、なんかもはやいぢめでしかない。
最終的に世論に求められる判断は、彼女は実験を続けるべきか、否かである。
自分は続けるべきであると思う。
論文がむちゃくちゃであろうが、泣きながら200回は成功したもんっていっていても、である。
実際、論文を読んだ人はどれだけいるだろう?
そしてその意味をすこしでも把握出来た人はどれほどの割合だろうか。
STAP細胞200回以上の感覚をどれだけの人が理解しているだろうか?
生命科学の実験はまさに料理のようなものだ。
同じ素材をつかって、同じようにやってもなかなか同じものはできない。
そして論文は料理のレシピにあたる。プロトコルなどはそのもまさにレシピだ。
料理人がかわり、キッチンも道具もかわれば、レシピどおりに料理を再現しようとしても、なかなか再現できるものではない。
レシピのために撮影された写真が、加工や転用された他のものであったとしても、レシピの本来の機能を奪うものではない。
レシピや制作日記だけで料理が存在したことを証明しようとするのが無理筋なのだ。だから一番シンプルな方法は存在を証明するなら料理を作るよない。
料理のために必要なスキルと、レシピにまとめ上げるスキルや綺麗な写真をとる技術はまったく別ものだ。
論文におかしい部分も倫理的にやっちゃダメなこともいっぱいあるのだろうけれど、たとえ全ての提示データが捏造だとしても批判に回っているほとんどの人が今回の論文ほどの構成のものが書けるとも思えない。
※博士論文はあまりにもあれなのであれしてください
あさがおの観察をしたことはあるだろうか?
「あさがおのタネが発芽するかどうかを確認する」という実験に、一回の実験にタネをひとつづつ植えるという計画しますか?
温度はどうだったのか、水はやったらどうなるのか、やらなければどうなるのか、もしかしたら種ごとに芽がでたり出なかったりするのではないか。
可能性を試すためにバリエーションを変えたり、もしくは同一条件にしたり、と、いくつも同時に比較できるように実験をするのでは?
「あさがおのタネがいくつ芽吹くのを確認しましたか?」
「200個です」
こんなやりとり、
「あさがおは1年草だから200個の発芽を確認するには1年じゃ終わらない!」
こんな指摘にどれほどの意味はあるだろうか。
マイクロチューブとかがホルダーにずらっと並んでいる映像とかを見たことはないだろうか?
こんな感じの
http://item.rakuten.co.jp/orange-benri/nas2-5054-02/
培養するのに8時間とか数日かかるんだから、普通バリエーションごとに一回に12発とか、24発とかいくつも同時並行でやる。
逆に一回に一個しかしなかったら、比較対象がなくなり何が原因で失敗したか判断できなくなる。
2年で200回がありえない、だからやつは地獄の劫火に焼かれるべきものである!とか言っちゃってる人は、もう泣きながら毎年あさがおのタネを一粒づつ植えていけばいいのではないかと思う。
何個失敗したのかも言わず、発芽は200個は確認しました!って言っちゃうほうもほうなんだけどさ、でもね、実験のうまさと体系だてた報告のうまさは擬似相関だからね。
「あさがおのタネもらったけどヒマワリが咲いたよ!」っていうヤツがいたら、そりゃ普通、先生はおこるのかもしれないけれど、
「先生、わたしタネすり替えてません。」って泣きながら言うんだし、しかもそこに再現性があるって本人が言うんだから、ちゃんと追いかけなきゃダメでしょ。
STAP細胞が小保方氏が報告したような多機能性の獲得じゃないにしても、何かあることになるし。その何かっちゅうのも、単純に本人の証言を信じて、ともかくやらせてみようというというだけじゃなくてね。
写真はでたらめだとしても論拠はこの論文で十分だとおもうけどね。
ま、ES細胞は使ってないのでコンタミはないって言ってたけど、問題になったFigure 1のiのマーカーレーンにES細胞ってあるんだがな・・・
げふんげふん
子供の頃、腹赤イモリを飼ってたんだよね。
イモリは、イモリ同士のケンカで腕を噛みちぎられたとしても、生えてくることがある。生えてこないこともあるけど。これが、再生力で、人間のような哺乳類からは失われた機能。
傷跡程度なら塞がるけれども、皮膚の細胞は皮膚の細胞にしかならないので、失われた腕が生えるようなことはない。プラリアナのように刻んだ数だけ頭まで再生するというなこともありえない。だけれども、人間もナメック星人みたく腕とか再生したら便利だよね。目とか腕とかとれても大丈夫だし。
肝臓とか腎臓とかやられて透析とかになっても、はいこっちで培養して復活しておいたよ!みたいな。っちゅうことを夢見て再生医療の分野の研究はながいことやられていたわけですよ。
で、とうとう1950年代、受精卵で体細胞クローンができるようになるわけですね。どの細胞にもなれる未分化の受精卵に遺伝子ぶっこむことで同じ遺伝子の別個体をつくることができる。でも、ぶっこまれたほうの受精卵は、独立したその個体としての生命を奪われるわけで倫理的に、どうなんじゃろと。
で、2000年代にご存知の山中先生によるiPS細胞、つまり、分化しちゃった細胞も遺伝子いじくればもとの受精卵みたいに機能するんじゃね?って手法が発見された。絶賛世界はしのぎを削って莫大なお金と才能を投資して研究競争をしているわけです。
そこに今回、STAP細胞は遺伝子いじくらなくても、刺激与えれば、多機能性確保できるよ!って発見だったわけで、
おまえ歴史的経緯無視すんな!
俺らいくら時間と金をぶっこんでるとおもってんだよ!
人間はカエルやイモリじゃねぇんだよってみんな激おこなわけですよ。
で、注目高まって、肝心な論文の写真はこれ、だめじゃねぇかって。
ほんとに実験してんのかって。
博士論文とか引っ張ってきて、ほらこんなヤツだよって。
でもね、細胞外環境による刺激でなんらかの遺伝子発現がおきているのは、たとえ死滅細胞における発光現象だとしても、分野として面白いなーと思うわけです。
そんな19世紀にやりつくされたみたいな実験いまさらなんでよっていう話しなのかもしれないけれど、現代は遺伝子が発現したのを視認でトレースできるマーカーがあるわけですよ。
「哺乳類の腕を切っても再生したことはない」という観測事実と、「環境刺激により遺伝子の発現があることはない」というのは別なわけです。
今は細胞単位でその細胞がなんであるかが追えるようになったわけですから当然あらたなる発見もありうる。
たとえまとめた論文が科学倫理的にもおかしかったとしても、タイミング、着想としては面白いし、それを立証するためのスキーム構築はありなんじゃないかと。
こんな着想にたどり着いて、実験にとりくめたのは「未熟さ故に」ああいう論文になってしまったのかもしれないけれども、そこはかなり小保方さんは凄いとおもいます。ヴァカンティさんがすごいのかな?
つまり、レシピを見る感じ、作ったらけっこううまそうな料理できるんじゃねぇのと。思うわけです。もういっそのこと「写真はイメージです」とでも書いておけばよかったのにねw
でも、現象の報告に対して、科学的に反証や追証じゃなくて、倫理面での非難や、組織への非難、ひいてはパーソナリティへの攻撃はSTAP現象を報告したというもの以上の反応を獲得している様は、なんとも悲しい。
ノーベル賞の二度目の受賞にあったキューリー婦人でさえ、スキャンダルまみれになったことを考えれば、人がゲスリング部になるのはいたしかたがないのかもしれないけど。つくづく、ひどいなーと思うよ。
でも、断罪すべきであるとか、ぎゃーすかぷーすか言っている人たちよりも、そのひとらが言うところの「ダメな論文」のほうがよほどしっかり書かれているし説得力がある。
星新一賞の最優秀作品読んだ?あれよりよほどぶっとんでるw
余談だけど、エボラ出血熱がいまアフリカでパンデミクミクダンスしてるね。
なんかBSニュースの字幕で死者1,000人と書かれてた気がして、うゎぁと思ったんだけど、100人だったみたい。
WHOとか国境なき医師団のHPとかみると、感染地域が広く、もしかしたらさらに深刻な事態になるかもしれないなと心配しています。
チャレンジングだって。封じ込めに失敗すると人類近代文明存亡の危機に直結しちゃうね。
で、そのエボラ出血熱が日本に来た場合、バイオセーフティーレベル4を設備的に有している施設は日本国内には2つだけで国立感染症研究所と理化学研究所の筑波研究所しかないんだよね。
すっかりみんなの非難と好気の対象になってしまった理研だけど、なんだかんだいってもやはり国内有数。
いままでの成果を考えても設備的にみても尊敬にあたいする研究所だとおもいます。最先端研究がなんでこんなファンクなことになっちゃったんだろうね。
やっぱり割烹着報道あたりでポップスターにされちゃったからかね?
おまけ
成人ヒトの間葉系組織にMultilineage-differentiating Stress Enduring (Muse)細胞という新しいタイプの多能性幹細胞があることを発見しました。下等動物では臓器を再生したり、個体の断片から個体そのものを再生させるなど高い再生能力が見られ、間葉系組織に内在する多能性幹細胞が重要な役割を果たしていることが分かっております。しかし高等動物では、複雑な生体システムを進化させるのと引き換えに再生能力は限られたものになっていくと考えられています。従ってヒトの生体にMuse細胞という多能性幹細胞が存在するということは非常に大きな発見です。もしかすると我々が考えている以上にヒトの体は再生能力を潜在的に持っているのかもしれません。
東北大学大学院医学系研究科 細胞組織学分野・人体構造学分野 出澤 真理
意外と、人間みたいな生き物にも再生能力というのは失われてないのかもしれないね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB
https://twitter.com/yanwalee/status/451664926692503552
http://www.stemcells.med.tohoku.ac.jp/greeting/index.html