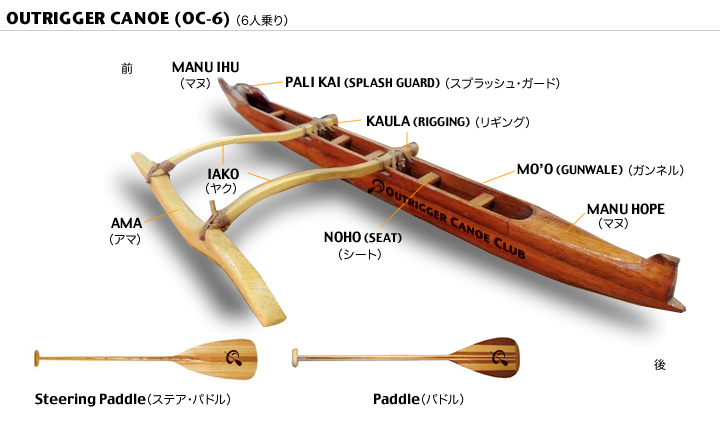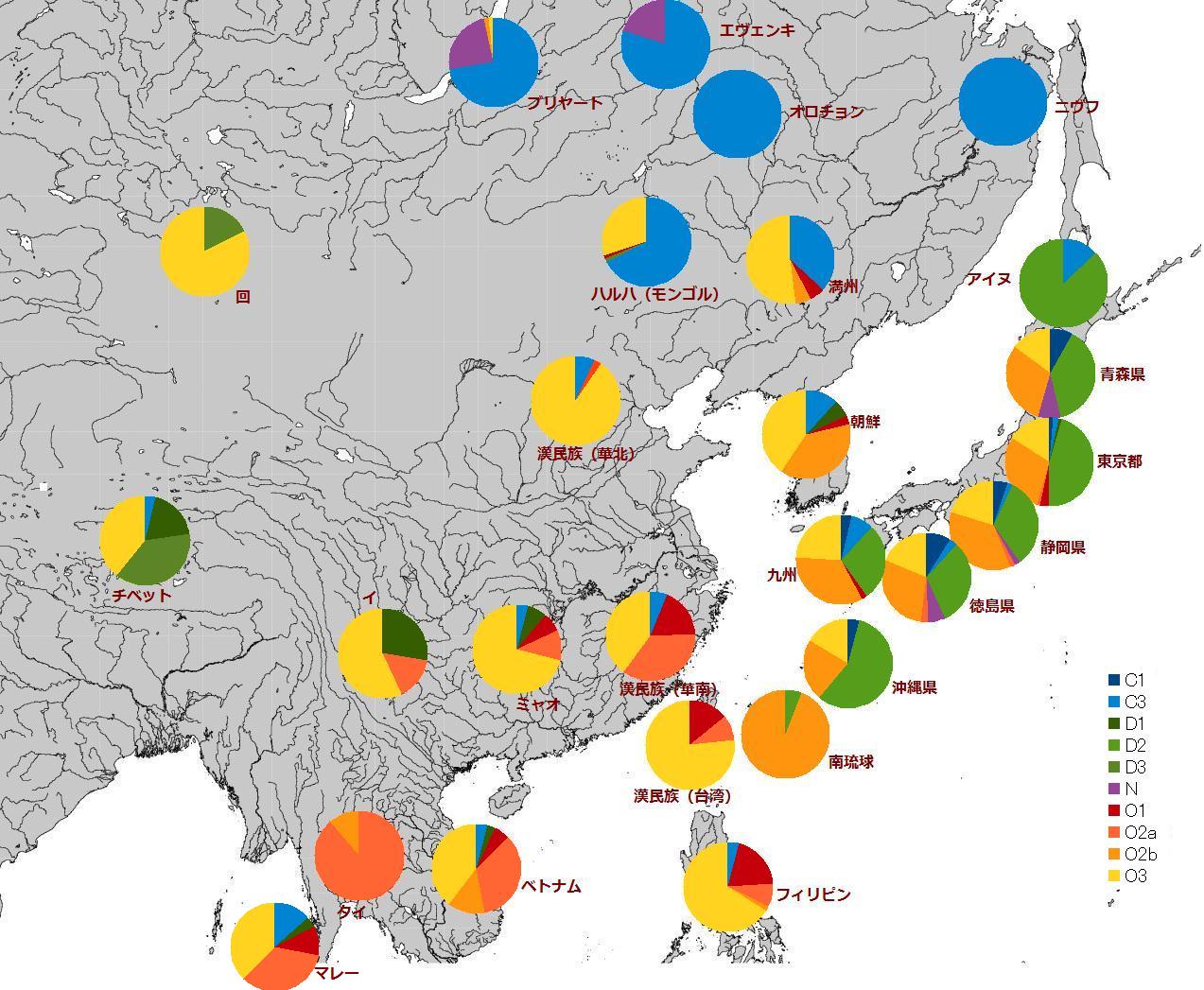1)神酒所設営、神輿、山車には、防災訓練に通じる合理があるのではないか
2)樹齢の高いご神木には災害忌避地のエリアログとしての性質があるのではないか
3)鳥居は、木造の自立構造を伝承するための技術現物見本としての役割があるのではないか
などについて書いてきた。
今回は、現代祭事から古代祭事ぐらいまでいっきにさかのぼって、お供え(神饌)について考えてみたい。
祭壇やお仏壇に、お米や、お酒、お塩、お魚、野菜、果物、お菓子あらゆるものをお供えする。
現在は様式化して、まあそういうもんだと形骸化、慣習化している。
なんでお供えをするんだろう?
なんで、そういう捧げ物の文化がうまれ定着したのだろうか?
宗教性をとりのぞいたときに、そこに合理性はあるだろうか??
お供えもの。その合理について考えてみたい。
市場機能
野菜や果物が並ぶ市、マーケットというのはどのような途上国にいっても見かけるものだ。市が開催されるようになることで、生産余剰を交換でき、貨幣が機能し、生産力の比較優位から結果として全体生産力が向上する。
日本での市の歴史をみてみると、織田信長が楽市楽座で規制緩和をおこなったことからもわかるように、行政を機能させるためには重要なポイントである。
鉄道や道路により物流に変化がおきるまでは、門前や参道はマーケットを開催するのに適した地であった。マーケットが開かれるからそこに神社が立つようになったのか、神社があるからそこに市が開かれるのか、その因果はどちらとも言えないが、多くの人が集まるポイントに特定誰かの住居ではない半ばパブリックな建築物があることには合理がある。
収穫物の収集と集約と評価、分配という機能があるのではないかと考えられる。
現在の魚市場や野菜市場は、全国からの集荷と、値決め、分荷が市場としての主な機能だが、古代都市は、集落、部族ごとの交易の場としての、マーケットにお堂をたてるのは合理性がある。
品種改良
マーケットに建てられたお堂、祠。これらは世界で類型がみられる。精霊信仰などとも大差のないものである。
しかし、日本の土着宗教において、とくに特徴的といえるのは作物、収穫物の神饌、捧げ物である。
ときに秋祭りなどでは顕著で、その年にとれた出来のいいも作物などを、神前に捧げたりする。
これに合理性はあるだろうか?
もしかして、400~800年頃の日本にいた偉人はその年の実りをあつめて、品質が良かったものを翌年に育てるということをしたかったのではないか?
冷夏が続いた年には冷害に強い稲が集まり、干ばつが続いた酷暑のあとには渇水につよい稲が集まる。
病害虫が続けば、それに強く生き残った稲が集まる。
それらを捧げると称して、だまくらかしてでも一同に集め、品評して、そして縁起物だからと払い下げる。植物が自力でその植生範囲を広げるより圧倒的な速さでその子孫が増えていき、歴々強く多く実る作物に品種改良がおこなわれていく。
日本に稲作伝承するまえは、栗や、栃の実など、どんぐりのような落実植物だが、これは品種改良をしようとしても、歳月がかかり無駄も多い。挿し木で分けてしまったほうが早い。が、稲の場合は1粒が1000倍にもなる。品種改良に成功さえすれば、その栽培効率の改善はおおいに期待してよいものだ。
1~3世紀に存在した邪馬台国の有力地とされる纒向遺跡(まきむく)から大量にモモの種が出土した。
祭祀に使用されたものと考えらていれるようだ。
だから、祭祀ってなんじゃいな。説明できないものを祭祀で片付けるのよくないよね。
山中で取れる自生の桃には現在のような甘いものは少なかっただろうし、苦味があるものもあっただろう。
甘く果肉たっぷりのものがたわわに実るさまは栄養事情に乏しかった中世以前、まさに神の御業のごとく見えたことだろう。
集めた種から、種苗育成をおこない植生を交換していく。より甘くなったものを、植え、さらに甘くなったものを探す。苦いけど病気に強いものと、甘いけど病気に弱いものをかけ合わせて、第一世代はどうなるか、など、研究しようとするならば不可侵の神域を定める必要がある。
古代に農作物の苗や種を提供してくれる農協のような広域組織はない。
化学肥料もなく、作物のバリエーションも少なかった。
いまではあたりまえに食べられている、じゃがいも、やさつまいも、かぼちゃ、トマトだって外来野菜だ。野菜や根菜で日本固有種というのは実にすくない。
冷害や渇水で作物が充分に収穫できないと直接生死に直結する。
海外から輸入もできなければ、冷蔵庫もないのだ。
弱者救済のための福祉や、再分配の要素。長老的な人物を祭壇に据えておくことで、これは毒キノコじゃ、こうやれば食えるというナレッジ共有、食育もおこなえたことだろう。
感謝するとかの建前はおいておいて、その年に採れたもの、その中でもいいものを、一箇所にあつめることには、
非常に理にかなっている。
中世の歌舞伎では一年にいちどその年に上演する舞台の世界定めをおこなったそうだ。その年にとれた作物を集めて、翌年に育てる種苗の世界定めをすることは、実に合理にかなっている。
参考
市場の役割と機能
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/about/useful/
奈良・纒向遺跡で大量の桃の種 邪馬台国の有力地
2000個超、祭祀に使用か
https://id.nikkei.com/lounge/auth/password/proxy/post_response.seam?cid=16244431
神道Q&A♪ > お供え物…右?左?♪
野菜をお供えするとき、向きはありますか?
http://isuzujinja.blog103.fc2.com/blog-entry-275.html
なぜ美味しい野菜ができるのか種農家に聞いてきた
http://genryudaigaku.com/archives/2924