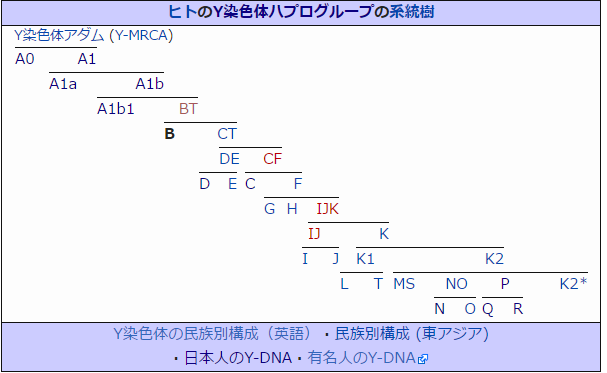楽曲の著作権を管理するJASRAC(日本音楽著作権協会)が音楽教室からも著作権料徴収をするとして反感がわきあがっている。
音楽教室は儲かってそうだから上前ちょっとよこせ?
著作権を守らせるためには音楽文化を根絶させることも辞さないような愚かな行為だ。
音楽教室から著作権料徴収へ JASRAC方針、反発も
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170202-00000014-asahi-musi
JASRACの外部理事 東京大学先端科学技術研究センター 玉井克哉教授のツイートを伺うに、
「放置」していたのではありません。こころよく払ってくださる事業者もあるのに、最大手で全国に何千もの教室を展開し、数百億の売上を挙げている事業者が「ビタ一文払わん」と頑強におっしゃる。十年以上お願いしても態度が変わらない。これでは正直者が馬鹿を見るので、腰を上げるしかったのです。 https://t.co/Au3kcUPht4
— 玉井克哉(Katsuya TAMAI) (@tamai1961) 2017年2月3日
音楽事業で利益があがっているから(取り立てる側が)泣き寝入りはしないぞということらしいです。
小さい音楽教室なんかは対象外だから心配するなってのも部外者からするとなんじゃそりゃ感。恣意的運用もいいところ。法を背景にうごいている人たちがこんなことをしてていいのかな?
音楽や文化振興の未来を蝕んでいるんじゃないのかな?
日本の子どもたちの未来になにしちゃってくれてるの??
それこそが目的なの?
プロのミュージシャンが他人の著作楽曲をつかって観客から入場料をもらうのが営利事業なのはわかるし、そこから入場料のいくばくかを楽曲の製作者に還元するというのもわかる。で、その徴収行為をそれぞれが行うのは大変だから管理団体が立ち上がるのも、まあわかる。
で、なんで練習や教育にも著作権侵害が絡んでくるの?というのが素直な疑問。
音楽著作権について
一般に学校教育などにおける授業において著作権の侵害は発生しておらず著作権料の支払いは不要とされている。
著作権法
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s2.3.5
(営利を目的としない上演等)
第三八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
学校が音楽著作物を利用できるのは非営利目的であることと、聴衆から入場料などを得ていないこと、演奏者に報酬を払っていないことが法的な建付けになっている。
せっかくなのでJASRACのホームページからその主張を考えてみたい。

http://www.jasrac.or.jp/copyright/outline/index.html
今回は音楽教室は著作財産権うち上演権・演奏権について音楽教室は営利目的の団体だから違反しているじゃないかという論のようだ。生徒が教師に対して、もしくは教師が演奏しているから、伴奏などで楽曲を演奏するからが論拠のよう。
かつては、カラオケはただの楽曲の私的利用ではないかという係争もあったようだが、カラオケの機械が演奏者で、カラオケを唄っている客こそが聴衆。で、聴衆がカラオケボックスに入場料を払っているのだから営利目的の演奏にあたるのでアウトだということのようだ。んんん?と思わなくもないけれども、まあ録音楽曲を営利で公衆送信をおこなっているのでまあなんというか、うん、まあ、うん。
学校はオッケーだけど、音楽教室はアウト。
学校法人はオッケーだけど、塾はアウトみたいな感覚なのかもしれない。
だが、最大手のひとつヤマハ音楽教室は、一般財団法人ヤマハ音楽振興会が主体となっていて、公益目的の法人である。一般財団法人は拠出された財産を運用する目的の団体だ。法人の性質上余剰金の分配はおこなわれない。財務諸表などをみてみると経常収益は260億円であるが経常費用は266億で今年度循環でみるかぎりは赤字である。流動資産が78億、固定資産が22億(固定のほうが少ないって珍しくね?)で、利益を伸ばしているようにも見えない。
http://www.yamaha-mf.or.jp/activity/setsuritu.html
こんな論もある。
「生徒は講師の演奏を聴くために授業料を払っているのではない」「教師は演奏の対価として給料をもらっているのではない」
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kuriharakiyoshi/20170206-00067411/
しかし、その理屈がとおるならば学校法人だって利益をあげているじゃないかと言うことができてしまうはずだ。多くの学校法人もその運営のために毎年余剰金を積み立てているはずで、それは貸借対照表上はまぎれもなく利益だ。
管理楽曲の利用があるだけで「教師は演奏の対価として給料をもらっている」ことの可能性を排除することは難しい。
JASRAC管理下の曲が一曲紛れ込んだだけで、すべての商行為がライセンス感染する。オープンソースソフトウェア界隈であるGPL汚染というか、ポイゾニングなみの恐ろしさがある。本来はその楽曲の貢献度、影響度について計算したうえで”それ”はなされるべき性質のものだが、枝葉末節であったはずの音楽のしかもたかだか数曲のしかも数フレーズが、その外を無視して結果すべてにかかってくるのだ。
音楽教室のあげる利益の源泉が楽曲利用にあるのであればそれもよいかもしれないが、どう考えてもそうではないだろう。
喫茶店が楽曲を利用していからJASRACが来たり、ライブハウスでアマチュア出演者が演奏するからというのでJASRACが来たりしていたけれども、とうとう、教室にまで進出してきたかという感じ。
巨大な利権と天下り先か?
天下りが問題になるのは、天下る人の問題じゃなくて、辞めた人が現役現場に影響力を持ち続けることができる現場の膠着性。またはそれを維持するための法的参入障壁と寡占市場のほうにこそ問題の根幹があるとおもう。なので、天下りとか利権をどうこういうことの意味を感じはしないのだけれども、ツイッターなどの意見がそこに集まっているようなので、財務についてのほうには触れておこうとおもう。
情報公開 (業務及び財務等に関する資料の公開について)
http://www.jasrac.or.jp/profile/disclose/index.html
一般会計と信託会計にわかれていて、信託会計の収入の部をみてみると手数料収入は1638億円に登る。演奏や放送の徴収額と支出額が億、十億単位でずれているが、どうしてなのか俺には推測もできない。
「JASRACの給与・役員報酬の合計は約36億円」というツイートもみかけたのだが、正確には2015年度の役員報酬は2億3千万、6億2千万である(管理費)。事業費のほうの給与(たぶんこちらは一般社員のほう)は33億7千万。
正味財産増減計算書
http://www.jasrac.or.jp/profile/disclose/pdf/2015/2015_general02.pdf役員等一覧
http://www.jasrac.or.jp/profile/outline/officer.html常任理事以上9名
理事22名
監事4名 の計35名。
一般理事はほとんど費用をもらっていないなどの事情でもなければ、それほど膨大な報酬を得ているとは思えない。ただ、信託会計収入合計1,638億、一般経常収支143億もありゃ、この管理団体の収入だけで電子書籍市場の規模1,800億に相当するわけで、絶大な影響力があるのは想像に難しくない。
音楽著作権管理団体にはJASRAC以外にe-Licenseなど後発もあるが、こちらは資本金6億の株式会社だ。ここらへんに触れだすと包括契約がどうこうとかいいたくなるのでやめるけど、まだまだ寡占市場であることは間違いない。
かんそー
「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)
著作権や知的財産権の根幹にあるものは、頭の外にだされ固定化されていなければならない。頭の中にあるだけのアイディアなどは保護されないのだ。
音楽の場合、表現が楽譜やメディアとして記録されるようにできるようになったためにどのようにそれを管理すればよいか迷走している。果たして、誰かが表現した楽曲を、再び演奏者が表現し直すのはどこまでその類似性を許すのか。
コード進行は?メロディーの類似性は?それ本当にAIとかで楽曲類似判定かける時代になっても別の曲だと言いきれますか??
俺には日本の有名なあの曲だって外国のあの曲にしか聞こえないものが多くある。
リスペクトとパクリとマッシュアップは同じもの?
外国の民謡を自分が作曲者だといいはる人物を守るのが本当に文化振興事業なのでしょうか。
著作権の考え方のベースになっている万国著作権条約がつくられたのが1952年。まだ60年ちょっとしか経っていない。しかし、この60年のあいだに出版物や音楽を取り巻く環境は大きく変わった。音楽の演奏形態もおおきくかわった。
ネット配信が主流になった今では、曲はフリーで配布して、コンサートやグッズで稼ぐなどアーティストの利益回収のための仕組みもかわってきた。
だからといって、手数料収入がおちてきたから音楽教室に手をいれようとか、そんなタコが足くうようなことしてちゃだめだよね。いい大人が考えたアイディアがそれじゃ筋がわるすぎる。いったいどこらへんが音楽文化振興なんですかと。
もしかしたらこんなことも今話題の文科省の天下りあっせん調査がすすめば解決したりしてね。
もし学校の授業で私の曲を使いたいっていう先生や生徒がいたら、著作権料なんか気にしないで無料で使って欲しいな。https://t.co/34ocEwCj8K
— 宇多田ヒカル (@utadahikaru) 2017年2月4日
参考
音楽教室でJASRAC管理楽曲は「演奏」されているのか。
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2017/02/jasrac-3747.html
→弁護士の見解
宇多田ヒカルさんは勘違いされているのではないか?
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kuriharakiyoshi/20170205-00067379/
→ 弁理士の見解
https://togetter.com/li/1077579
→ JASRACの外部理事 東京大学先端科学技術研究センター教授の関連ツイート
残酷な天使のテーゼの作詞者「音楽はタダではない。でも音楽を学びたい子供達には自由に使わせてあげてほしい」
https://togetter.com/li/1077289